「腸内細菌が共生できているのは、どの菌にも何らかの有益な作用があるからだと思います」(竹田潔インタビュー①)
腸と健康の関わりが語られるようになって久しいが、最先端の科学の分野ではいったいどこまでが解明されているのか? 消化管である腸の働きと切っても切れないのが、生体防御機能を担う免疫の働き。大阪大学医学部でインターロイキン6の発見者である岸本忠三、自然免疫(トール・ライク・レセプター)のメカニズム解明に貢献した審良静男という免疫学の第一人者にもとで学び、免疫と腸内細菌の関わりに新たに着目、炎症性腸疾患ついての研究に取り組むようになったのが、今回インタビューをする竹田潔氏(大阪大学大学院医学研究科教授)だ。難病として知られる潰瘍性大腸炎、クローン病などの解明を通じて、体内の共生者である腸内細菌と免疫の関わりをどう捉えるようになったのか? 免疫・代謝・食事の意味など生命活動の核心について、2回に分けてインタビューをお届けしたい。

■腸内細菌が排除されないのはなぜか?
――先生のご専門は、潰瘍性大腸炎やクローン病など、腸で起こる炎症性疾患の研究ということでしょうか?
竹田 そうですね。そうした病気がどうして起こるのかという点に一番興味を持って研究していますね。
――それはもう一貫して?
竹田 はい。十数年前に研究室を持つようになったんですけども、その時から研究を続けています。
――腸、炎症、免疫が切っても切れない関係であることが知られるようになってきましたが、それは難治性の疾患だけではなく、一般的な病気に対してもカギを握っている印象があります。実際、「腸が健康の要だ」といった内容の本もいっぱい出ていますが……。
竹田 そうですね。流行りなのかすごく出ていますね。
――僕もそういう本をたくさん作ってきたのですが、先生は腸と健康の関わりをどうとらえてらっしゃいますか?
竹田 まず、免疫系と腸内細菌の関係を考えた場合、マウスを用いた研究では腸内細菌が存在して初めてリンパ球が正常に発達してくるということがわかってきています。それは、腸内細菌がない「完全無菌マウス」ではリンパ球が成熟しないという事実から来ているわけですけれども。
――なるほど。腸内細菌の存在が無視できないわけですね。
竹田 それと相まって、近年、次世代シーケンサー(遺伝子の塩基配列を高速で読み出せる装置)を用いて1000種類を超えるような腸内細菌が、どのような割合で存在しているのかが判明しています。その結果、マウスの実験になりますが、腸内細菌叢の割合が異なることでリンパ球が異常になるなどの事実もわかってきました。
――人に関してはどうでしょうか?
竹田 様々な病気の中で、腸内細菌叢の乱れとの関連がわかってきていますね。腸内細菌叢の乱れが認められる病気の多くは免疫系の異常、リンパ球の異常が確認できるという事実もあります。「腸内細菌叢の乱れ」がいくつかの病気には関わっていることは明らかだろうと思います。
――腸内細菌叢は「腸内フローラ」とも呼ばれていますが、これは大腸が主ですよね? 細菌が一番多い場所という意味で……。
竹田 はい。大腸が一番多い場所です。
――その一方で、免疫は小腸の働きという印象がありますが。
竹田 いや、そういうわけではなく、小腸にも大腸にも免疫細胞は存在していますよ。
――ただ、割合で言うと消化吸収を行う小腸にリンパ球も自然免疫も含めて集まってきますよね? やっぱり小腸が免疫の中心というイメージがあったのですが、そのあたりのとらえ方は実際どうなんでしょうか?
竹田 消化管としては小腸のほうが長いので、結果としてリンパ球の数も多いですけれども、大腸にも相当な数が存在しています。小腸と大腸に存在しているリンパ球の数が体内でもっとも多いんです。
――6~7割ぐらいと言われていますよね?
竹田 正確にはなんとも言えないですけれども、一番多いだろうと。そこで一番不思議なのは、免疫の基本的な使命というのは「異物を認識する・排除する」ということですが、一方で、毎日私たちは食事をしますし、しかも大腸には腸内細菌もいて、どちらも免疫細胞にとっては異物なんです。しかし、腸内細菌に関しては異物として認識することも、攻撃することもなく、健康な状態では何もしていないわけです。
――これは「免疫寛容」と呼ばれるものに含まれますか?
竹田 そうですね。
――文字通り非常に「寛容」だと。病原菌やウイルスは免疫で排除されますが、いわゆる腸内の悪玉菌と呼ばれる菌はそのまま住まわせるというか……。何をもって免疫は判断しているんでしょうか?
竹田 そこがわかっていないんです。何をもって判断しているかとなると、腸内細菌もやはり免疫細胞と出会わせると異物ですから、明らかに免疫は反応するようになるんです。
――反応はしていると?
竹田 はい、免疫細胞は腸内細菌を直接認識すれば必ず反応します。その結果として出てくるのが、潰瘍性大腸炎やクローン病のような炎症性腸疾患というわけです。炎症性腸疾患は、健康な人では反応しない腸内細菌に免疫細胞が反応するがために起こっている病気と現在では認識されているので……。
――逆に言えば、普通は反応しないわけですね。イメージしにくいのですが、直接出会っていないということでしょうか?
竹田 普段、腸内細菌は消化管の内腔だけに潜んでいて、上皮の壁を越えたところにある免疫細胞と出会うことがない、だから免疫反応が起きない。一方、病原細菌は上皮の壁を越えて入ってくるので、免疫は反応するということだろうと考えられています。
――なるほど。侵入して来るものに対しては……。
竹田 必ず免疫細胞は反応します。
――もちろん攻撃もすると思うんですが、そこまでしない共生菌で、あまり有益でないものを放置するということは?
竹田 どうなんでしょうね? ヒトは腸内に1000種類を越える腸内細菌を持っていると言われていますけれど、直接的に影響を及ぼさなくても腸内細菌同士で影響を及ぼしあっていますから。
たとえば、食事から食物繊維を分解して短鎖脂肪酸を作り、それが上皮細胞のエネルギー源になると言われていますが、これは一種類の腸内細菌が作るわけではなく、様々な腸内細菌の連鎖で結果として栄養素ができてくるので、どの菌にも何らかの(有益な)作用があるから、わざわざ腸に住まわせているということかもしれません。
■腸内細菌が栄養吸収の媒介になっている
――どの腸内細菌も何かしら働いているだろうと。よく「日和見菌」という言い方がされますが、竹田先生の認識の中では「何もしない」わけではない。それなりに意味があるからここにいるんだろうと……。
竹田 ええ、そういう認識ですね。だから無駄なものはそんなにいないんじゃないかなと、無駄なものなら腸内には住めないと思いますので。つまり、お互いがお互いを利用できるから細菌たちも生活できる。こういう連鎖の中に入っていない細菌はもう住めない。
――なるほど。
竹田 やっぱり微生物も賢い生物で、微生物間のコミュニケーションの中でお互いがお互いをヘルプしあっているはずなので、そういうところで無駄なものはないんだと。そこには腸内細菌にとって無駄ではないという観点も入ってきますけれども。
――複雑すぎて全容を解明するのは難しいと思いますが、何かしら連携しあいながら共生しているということですね。もちろん食べた物の内容とか、宿主である我々のストレスとか、いろんなものが作用して、それが腸内細菌叢の種類や分布を決めるのでしょうが……。
竹田 それはもう、エビデンスとしてもありますね。たとえば、草食動物と僕たち人間を比べると、明らかに腸内細菌叢が違うんですね。草食動物は植物からタンパク源を得ているわけですが、それは植物をからタンパク源を作り出すような腸内細菌がそこにいるということです。一方、ヒトは肉などからタンパク源を直接摂っているので、そういう腸内細菌を必要としない。だから、ヒトの中にはいない。簡単なところでは、そういう事実があります。
――食性が違うから、当然、菌叢も違う。それぞれがそれぞれの形で健康を保っているということですね。
竹田 同じヒトの中でも住んでいる地域、たとえば肉を多く食べる西洋、日本も最近はそうなってきていますが、それとは反対に、いまでも穀物類が主食の地域もあり、それぞれを比べると、もう根本的に腸内細菌叢が違っています。ですから、食べる物をいかに利用するのかというところで腸内細菌が異なるということだと思います。
――栄養学の方面から勉強していくと「成分」の勉強をしますけれども、それはあくまで人の体の代謝にどう役立つかであって、それが菌にとってどう作用するかという視点が欠けているように感じます。
竹田 まあ、僕の観点からすると、健康な人であれば、穀物ばかり食べる人たちも、肉ばかり食べる人たちも「吸収する栄養素」という点ではほぼ同じだという認識がありますけどね。
――ええと、吸収する栄養素というのは……。
竹田 その栄養のもとになる食べ物は根本的に違うわけですよね。違う食べ物を同じ栄養素にする、このリンクの部分に異なる腸内細菌がいるんだということです。だから、いろいろな食物を好む腸内細菌がいるわけで、人としても「自分自身の健康の維持に必要な腸内細菌」を腸内に住まわせていると考えるほうがいいと思います。まあ、人が先なのか腸内細菌が先なのかは永遠にわからないことですが……。
――お互いに持ちつ持たれつということですよね。
竹田 ええ、そうなんですよ。
――そうした関係性がこの世界で生きることの基本になっている。それって、すごく不思議ですよね。
竹田 ええ、すごく不思議です。
■50年前の日本人の腸内細菌叢を見てみたい
――腸内細菌の研究もだいぶ進展していると思うんですが、体感的なレベルで言うと、お腹の調子が悪い時、便の状態が臭かったり、硬かったり、いろいろと変化がわかります。と言うことは、腸内細菌叢も変化しているはずで、腸内細菌に食べ物がどんな影響を及ぼすかも考慮しないと、何を食べて健康になれるのかわからないと思うんです。
竹田 腸内細菌でいかに健康を維持するかということでしょうか?
――栄養学で提唱している食事のモデルがありますよね? それが間違っているとは言わないまでも……。
竹田 なるほど。どんな食事を摂ればいいのか? おっしゃるように地域ごとの特性を出すことも必要だと思いますが、ただ、いまは西洋の栄養学がベースでもいいかもしれません。日本人の腸内細菌もいまは西洋型ですので。
――西洋型になってしまった?
竹田 もう、ほぼ同じです。だから、僕の興味として50年前の日本人の腸内細菌叢を見てみたいという思いはあります。それはどうしょうもないんですけどね、おそらく違うと思いますよ。
――多分、そうですよね。
竹田 炎症性腸疾患という病気も、この30年で10倍にも20倍にもなっているんです。たとえば、エビデンスのある話ではないですが、病気って基本的に遺伝子的におかしなところで発症する場合と、環境因子によって発症する場合と、二つありますよね? この二つの複雑な絡み合いで様々な病気が起こるといいますが、遺伝子のほうがこの30年で一気に変わるはずがありません。だから、環境の変化によるところが大きいのでしょう。佐古田三郎先生の研究されている多発性硬化症もそうですが、この30年で患者が急増しているのは、明らかに環境が変わってきているからですよ。
――遺伝要因より環境要因ということですね。
竹田 わかりやすい例では、この50年くらいの間に日本人もみんな肉を食べるようになってきました。50年以上前はなかなか食べることもなかったわけですから、これは大きな変化ですよね。
――食生活はものすごく変わったと思います。
竹田 50年前の日本は穀物類がタンパク源だったわけで、その後、腸内環境が西洋と同じようになって来て、炎症性腸疾患も増えてきた。そういった事実から言っても、おそらく腸内細菌叢も西洋型になって……。いや、実際に西洋型ですからね、そこに原因があることは十分に考えられます。エビデンスを取るには50年前の細菌叢を見ないといけないので、証明するのはもう絶対に無理なことなのですが。
――便が保存でもされてなければ。
竹田 ないですからね。だから、50年前の栄養学なら50年前の腸内細菌叢に合わせた栄養学というものを考えなければいけないでしょうけれども、今はもう日本人も西洋型の腸内細菌叢なので、欧米から輸入した栄養学でも問題はないだろうと、そういう見方もできますね。
――ただ、欧米型の腸内細菌叢で、炎症性腸疾患や多発性硬化症、パーキンソン病も増えていると言うことは、その食事を変えていけばそういう病気も減っていく可能性はあると。
竹田 そうです。肉を食べるのを減らして、50年前の粗食に戻していけばこうした病気は減っていくと思いますよ。ただ、一般の方に「牛肉を食べるのをやめろ、脂物をやめろ」と言うのは、なかなか難しいかもしれません。だって、病気になる人はそれが好きで食べているわけですから。炎症性腸疾患の場合、患者さんは10〜20代の食べ盛りで、そんな世代に「脂物はやめて煮込み料理ばかりにしなさい」とは言いにくいところがあります。
――よっぽど親御さんが努力するとか、実践は大変かもしれないですね。
竹田 病気の人に実践してもらえば、10〜20年かけて病気の数は減らしていけると思いますけれど、病気になっている人にそれをすすめたところでもう遅いんです。そこの問題がどうしてもあるので、食事指導も難しいというのが現実としてあると思いますね。
――潰瘍性大腸炎などは、原因がまだはっきりわかっていないんですか?
竹田 わかっていないですね。
――何か手がかり的なものは? 遺伝ではないんですよね?
竹田 遺伝も関わっていますが、それだけではないです。僕が思っているのは、クローン病と潰瘍性大腸炎という二つの炎症性腸疾患の病気がありますが……。
――年齢層でいくと、どの年代が一番多いんでしょうか?
竹田 クローン病と潰瘍性大腸炎の厚生労働省の登録数ですが、1980年代からどちらも一気に増えてきています。患者数ではなく、発症年齢になりますが10〜20代。発症した人が治らなければ患者数はどんどん増えていくことになります。
――突然なってしまう感じなんですね。
竹田 突然、腹痛や下痢が始まって、どうにもそれが治まらないという感じでしょうかね。
――IBS(過敏性腸症候群)とも違うわけですよね?
竹田 全然違いますね。
――向こうは心因性だと言われていますが……。
竹田 (心因性とも)違いますね。この病気がどうして起こるのかというところで、クローン病も潰瘍性大腸炎も患者さんごとにいろいろな症状があるので、臨床の先生方は非常に複雑な疾患ということで困っていますが、僕の場合、基礎研究をやっている立場ですから、シンプルに免疫系と腸内環境の両面から考えるようにしています。
――やっぱり腸内細菌が関わってくるんですね。
竹田 消化器科のIBD(クローン病、潰瘍性大腸炎)の先生方にも納得してもらっていることなのですが、基本的にこうした病気は、遺伝的素因として免疫系の異常・暴走、あとは腸内環境の異常という二つの因子が相まって起こります。ただ、たとえ免疫系が暴走する素地があっても、たとえ腸内環境がおかしくなっても、片方だけでは絶対に病気は起こらない。両方の因子があっても病気が起こらない人もいますが、片方だけというのはありません。
↓続きはこちらをご覧ください。
★「腸内で免疫寛容が生じるカギは、ムチンでできた粘液層にあると思っています」(竹田潔インタビュー②)
◎竹田潔 Kiyoshi Takeda
1966年、大阪生まれ。大阪大学大学院医学系研究科教授。専門は、免疫制御学、粘膜免疫学。1998年、大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了。兵庫医科大学医学部助手、大阪大学微生物病研究所助手、九州大学生体防御医学研究所教授を経て、2007年より現職。大学時代より岸本忠三、審良静男氏のもとで学ぶ過程で免疫と腸の炎症性疾患の関わりに興味を抱き、サイトカインシグナル伝達の分子機構の解明、消化管粘膜免疫機構の解析、自然免疫機構の解析などに従事。独立後、潰瘍性大腸炎やクローン病などの解明に取り組んでいる。http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/ongene/
投稿者プロフィール
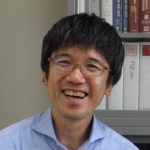
最新の投稿
 長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない
長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?
長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?
長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?
長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?



