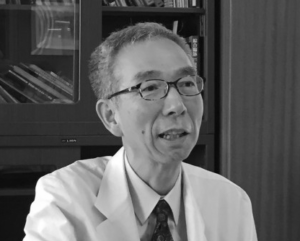「いずれアレルギーという病態がどんなものか、完全に把握できる時代になるでしょう」(斎藤博久インタビュー②)
ここ数年、アレルギー研究の分野で新しい発見が相次いでいる。「T細胞(Th1/Th2)のバランスが崩れることで発症する」といった従来の定説が見直しを迫られる一方で、アレルギーという病態の全容が徐々に浮かび上がりつつある状況にある。いまこの分野の最前線でどんな研究が進められ、何が明らかになってきたのか? このほど刊行された一般向けの『Q&Aでよくわかるアレルギーのしくみ』(技術評論社)の著者で、同分野の研究の第一人者である斎藤博久氏(国立成育医療センター研究所副研究所長/日本アレルギー学会理事長)へのインタビューを3回にわたってお届けしたい。今回はその第2回。

■アレルゲンを遠ざけても食物アレルギーは防げない?
——戦後の日本に限らず、文明が発展して、近代化していくことで、医療を受ける環境はドラスティックに変わってきました。そのなかで、病気が減ったというより、かかる病気の種類が変わったという面があると思うのですが……。
斎藤:ええ、それはそうですね。社会が清潔になり、衛生環境が改善されたことで、感染症は減りましたが、アレルギーは増えていますから。ただ、アレルギーの増加に関しては、アレルギーを起こしやすい食べ物を子どもに食べさせなくなったことも関係していると思います。特にアメリカなどでは、ピーナッツを食べさせないようにしたことで、ピーナッツアレルギーが逆に3倍に増えていますから。
——この話も意外に思う人が多いと思うんですが、アレルゲンになる食材を遠ざけても、食物アレルギーが防げるわけではないんですよね? 最近ではテレビなどでも取り上げられ、知る人も増えてきましたが……。
斎藤:一度アレルギーにかかってしまったら食べるのは控えなくてはなりませんが、最初に感作する場所は腸ではないわけです。
————食物アレルゲンも、腸ではなくまず皮膚から始まるということですね。乳幼児期の肌への保湿が大事だという話もここにつながってくると思いますが、アレルギーを持っている親御さんは、子どもが生まれるとどうしても神経質になりますよね?
斎藤:だから難しいところもあるんですが、そうしたナーバスな部分がアレルギー増加に拍車をかけた面もあるかもしれません。実際は、ちゃんと食べさせたほうが免疫寛容が働き、かえってアレルギーが防ぎやすくなるわけですから。
——前回のエンドトキシンの話もそうですが(→こちらを参照)、あまり潔癖すぎてもアレルギーは防げないというのは興味深いですね。
斎藤:エンドトキシンはアトピー性皮膚炎とは関係ないと思いますが、清潔志向が問題になるという点は共通しているでしょうね。まあ、清潔ということには変わりないのですが、アトピー性皮膚炎はほこりの問題ではなく、洗いすぎて皮の脂分を奪い取ってしまうのがいけないんじゃないかと思います。
——何でも一緒くたにはできない、個別に見ていく必要があるということですね。
斎藤:それはその通りですよ。皮膚に関して言えば、脂を取りすぎてしまうと皮膚全体が乾燥してガビガビになって細胞が壊れてしまうので、樹状細胞が突起を出し、アレルギー反応が加速してしまうという流れになります。
——それが皮膚で起こっている話で、気道のほうはまた別だということですね。
斎藤:気道の場合は、自然な状態だとアレルゲンがどんどん入り込む。そこに微量なエンドトキシンが出てくると、あたかも保湿剤を塗っているようにA20が出てきてくれて、バリア機能を補強してくれる。その結果、ぜんそくが防がれるわけです。気管支ぜんそくの場合は「清潔さ=エンドトキシン」、アトピー性皮膚炎の場合は「清潔さ=洗いすぎ」と考えればいいでしょう。
——皮膚の脂分の話が出ましたが、昔の人よりいまの人が少ないということは?
斎藤:それはないと思うんですけどね。体質が変わったのではなくて生活習慣でしょう。いまは赤ちゃんを、一日一回綺麗に洗っていますよね。昔も沐浴はやっていたけれど、水やお湯くらいでしょう。その違いはあるかもしれません。
——生活習慣が原因ということならば、そういう習慣をやめれば……
斎藤:そうなると、今度は皮膚病が増えてしまうかもしれないので、その意味では綺麗に洗って必ず保湿剤で脂分を補うようにすれば問題はないわけです。
——なかなかバランスが難しいですね。清潔になるのをまったくやめろというわけにもいかないですし、清潔になりすぎても問題は起こる。
斎藤:ただ、清潔にしたほうが赤ちゃん死なないですみますよね。
——ああ、大前提はそうですね。死亡率の上昇とアレルギーの増加を天秤にかけたら、現在のほうがずっと良い状況だと言える気はします。
斎藤:だから、清潔になるのはいいことなんだけれども、それをそのままにしておくとアレルギーがどんどん増えてしまうので、増えないようなことをしたほうがいい。たとえば保湿剤で補うとか、そういう話になってくるわけです。
■見直したい「ステロイドへの拒絶反応」
——先ほど神経質になりやすいという話が出ましたが、ステロイド剤の問題も無視できません。こちらも患者さんの間で違った意味での“アレルギー反応”があって、それが症状をひどくさせてしまった面もあるとおっしゃっていましたが……。
斎藤:そうですね。90年代の後半の頃のことなんですが、「ステロイドが怖い」というニュースが広がって、赤ちゃんに全然使用しなくなった。それで湿疹がひどくなった子どもが結構多かったんですね。最近は普通に使うようになりましたけど。
——たぶん、「衛生仮説」的な考えが広まるなかで「自然な生活がいい」とか「清潔にしすぎるからよくない」とか考える人が増え、その延長で「ステロイドのようなケミカルなものは使わないほうがいい」と考える人も現れていった気がします。
斎藤:かなりステレオタイプですけど、そういう傾向もあったかもしれません。「ステロイドは悪である」ということをいう人が多かったのは事実ですから。
――もう時効になってしまったと思いますが、ストロイドは危険だと報道したのは「ニュースステーション」ですよね?
斎藤:私が国立小児病院(現・国立成育医療研究センター病院)から国立相模原病院の小児科の医長に就任したのが94年1月なんですが、その年の5月ぐらいでしたかね、キャスターの方が「ニュースステーション」で「ステロイド薬は悪魔の薬です」って言ってしまったんですよ。それがすごくセンセーショナルな話題になって、ステロイド剤を塗っていた(アトピー性皮膚炎の)患者さんが一斉にやめてしまったんです。
――それでどうなったんですか?
斎藤:皆さん、悪化しちゃって。私のいた病院もアレルギー専門だから、たくさんの方が押しかけてきました。初診の患者さんだけで一日10人くらい診ましたし、1週間で3百人くらいの患者さんを診察して……かなり大変だったんですけどね。
――実際に過剰に使っていたお医者さんもいて、問題になったケースもあったのかもしれませんが、どうも情報が偏った形で伝わってしまうことが多い気がしますね。
斎藤:そうしたこともあって、アトピー性皮膚炎の赤ちゃんが一時期バッと増えているのですが、最近ではまた少しずつ減ってきています。ステロイド剤に対する拒絶反応も少なくなりましたし、保湿が大事だということも浸透してきましたから。
――なるほど、全体的には減ってきているんですね。むしろいまのほうが科学的に明らかになってきた部分も増えていますから、あまり過激にならず、バランスをもってアレルギー情報と接していける気がします。
斎藤:文明の恩恵というか、清潔にするためにいろいろなものを使っているのに、一方で「薬だから嫌だ」と言ってステロイドを使わないとか、あるいは、保湿剤も使わずに石けんでゴシゴシ洗うとか、片手落ちみたいなところはあると思いますね。
――文明化で得られるものは、メリットだけじゃなくてデメリットもありますから、それへの対処はしなければいけないということですね。
斎藤:そもそも自然の環境では私たち暮らせませんし、実際に暮らしているわけではありません。そんな環境に放り込まれたら、大部分の人が死んじゃうわけだから。
――概念としての自然志向みたいなものが、逆に足を引っ張ってしまっているというか。
斎藤:私たちに人工的に生かされているわけです。にもかかわらず、人工的なものを悪だと見なして拒絶すると、アレルギーが現れてしまう。
――逆の認識を持っている人もいるかもしれないですね。自然から離れてしまったからアレルギーが増えたのだという……。
斎藤:「自然に帰れ」というのは無理なんです。それでは乳児死亡率が何倍も何百倍も増えてしまいますから、健康でいられるはずはありません。(「自然に帰る」ということは)そういうことを意味するんだと知らないとね。
■2016年は「IgE抗体」発見50年の節目
――アレルギー研究の話に戻りたいと思いますが、2016年はIgE抗体が発見されて50年という節目にあたりますよね。これを機に、アレルギー研究の歴史を改めて啓蒙されるとか、意識していらっしゃることはありますか?
斎藤:50年目だから研究を変えようということはありませんが、数年前に自然リンパ球(ヘルパーT細胞)が発見され、重篤なぜんそくの発症に特に大きな役割を果たしていることがその後の大規模研究でわかってきました。IgE抗体を介したメカニズムもかなり明らかになってきていますが、その一方で、自然リンパ球の働きによってIgE抗体を介さずに炎症が起こることもだんだんとわかってきたわけです。
――アレルギーに対する概念もずいぶん変わってきたということですね。
斎藤:それまでは重篤なぜんそくもすべてIgE抗体で説明しようとしていたんですけど、それではやはり無理であったということです。
――より包括的にアレルギーという病態を捉えるところが、今後の課題でしょうか?
斎藤:課題はいろいろとあると思いますが、自然免疫の領域について、これからもっと研究しないといけないでしょうね。非常に重要であることはわかったんですが、ほとんどマウスによる治験ですから、ヒトでも重要だということはこれから明らかにしていく必要があります。ヒトとマウスで結構違う部分がありますから。
――いまおっしゃった自然リンパ球の話も今回の本に盛り込まれていますが、この数年の発見によって今後の研究の方向性が大きく開けてきた印象があります。
斎藤:まあ、IgE抗体が発見されて50年足らずで、IgE抗体を介したメカニズムが解明されて、大部分のアレルギー疾患の病態の説明がつくようになっているんですけど、どうもそれでは合わない部分があったわけですね。
――これからさらに研究が進むことで……。
斎藤:ええ、いずれアレルギーという病態がどんなものなのか、完全に把握できるようになるでしょう。大規模研究で網羅的に調べていくなかで、たとえばぜんそくに関しては、インターロイキン33(IL-33)のようなサイトカインであるとか、それに刺激される自然リンパ球が重要であることが様々なアングルから繰り返し出てきていますから、おそらくそれ以上に重要なものは出てこないんじゃないかと思うんですね。
――ということは、今後10年、20年の研究のなかで、アレルギーの全体像がほぼ解明されたと言えるような状況になる?
斎藤:ええ、大部分は見えるはずですよ。これだけ網羅的にやって調べているわけですから。その意味では、IgE抗体に次ぐ大きな発見がこの数年にあったということですね。
(第3回に続く)
↓続きはこちらをご覧ください。
★「ビックデータがいくら全盛になろうと、ロジックがなくなったら、それはもう科学とは言えません」(斎藤博久インタビュー③)
◎斎藤博久 (さいとう ひろひさ)
1952年、埼玉県生まれ。1977年、東京慈恵医科大学卒業。国立相模原病院小児科医長を経て、1996年より国立成育医療センター研究所・免疫アレルギー研究部部長、2010年より同センター副研究所長。2013年より日本アレルギー学会理事長。東京慈恵医科大学、東邦大学、東北大学などの小児科客員教授を兼任。米国アレルギー学会評議員、同学会雑誌編集委員、日本小児アレルギー学会理事なども務める。著書に『アレルギーはなぜ起こるか』(講談社ブルーバックス)、『Middleton’s Allergy 第8版』(分担)など。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない
長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?
長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?
長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?
長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?