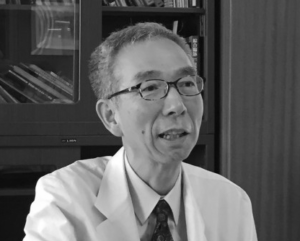「腸内で免疫寛容が生じるカギは、ムチンでできた粘液層にあると思っています」(竹田潔インタビュー②)
腸と健康の関わりが語られるようになって久しいが、最先端の科学の分野ではいったいどこまでが解明されているのか? 消化管である腸の働きと切っても切れないのが、生体防御機能を担う免疫の働き。大阪大学医学部でインターロイキン6の発見者である岸本忠三、自然免疫(トール・ライク・レセプター)のメカニズム解明に貢献した審良静男という免疫学の第一人者にもとで学び、免疫と腸内細菌の関わりに新たに着目、炎症性腸疾患ついての研究に取り組むようになったのが、今回インタビューをする竹田潔氏(大阪大学大学院医学研究科教授)だ。難病として知られる潰瘍性大腸炎、クローン病などの解明を通じて、体内の共生者である腸内細菌と免疫の関わりをどう捉えるようになったのか? 免疫・代謝・食事の意味など生命活動の核心について、2回に分けてインタビューをお届けしたい。今回は第2回(後編)。

■腸の上皮がストレスで弱くなっている?
――免疫と腸内細菌の関わりの中で起こると。
竹田 免疫細胞と腸管腔(腸内環境)との間に単層の上皮細胞があって、ここが健康であれば病気が起こらない可能性があるんだろうと、これがまず一つのアイデアです。クローン病と潰瘍性大腸炎という二つの炎症性腸疾患を比較すると、クローン病は小腸と大腸のところどころに飛び石状に症状が見られます。
――点在するんですね。
竹田 ええ。炎症が起こっているところは炎症細胞、免疫細胞がどんどん集まってきた結果としての肉芽腫ができます。その結果として、炎症が起こっているところは腸管壁が分厚くなってしまう、どんどんと炎症細胞がここに集まってきてしまう。一方、潰瘍性大腸炎は、直腸側、肛門側から始まる連続性の病変で、大腸にしか見られません。
――「大腸炎」なので大腸だけなんですね。
竹田 炎症が起こっているところを見ても、クローン病のように炎症細胞が集まった結果としての肉芽腫はほとんど見られず、いわゆる潰瘍という、上皮の障害がメインなわけです。それともう一つ、クローン病は家族性にも時々見られますが、潰瘍性大腸炎はそれほどでもない。家族性はクローン病ほどには出てこない。
――遺伝的因子の影響も異なるということですか?
竹田 はい。先ほどの遺伝的素因と腸内環境因子の関係を考えると、クローン病というのは、遺伝的素因、特に免疫系が暴走するような遺伝的素因があるような患者さんが多いです。実際にクローン病の遺伝子解析では、免疫系の遺伝子の異常が見つかっています。だから、クローン病というのはどちらかと言えば遺伝的素因があって、免疫系の暴走が起こったところが症状として点在しているんだろうと。
――なるほど。
竹田 一方、潰瘍性大腸炎については、遺伝的素因としては基本的には上皮なんだろうと。上皮のバリアがなくなれば根本的に生きていけないので、たとえばストレスなどで簡単に剥がれてしまうなど軽い異常があって、それが発症につながっている可能性があります。普段生活している限りは特におかしくはならないのですが、ストレスに上皮が弱い状態になっているのではないかと考えています。
――遺伝的に上皮が弱い傾向にあるわけですね。
竹田 それだけでは病気にはならないんですが、そこにひどい腸内環境の変化があれば、病気が起こってくる、それはバリア機能が低下しているから起こってくるんだろうと。
――臨床的にはもっといろんな複雑なバリエーションがあるにしても、その点をまずふまえたうえで治療に臨んだほうがいいということですね。
竹田 そうですね。病気をどのように治療するかということを考えた場合に、たとえば免疫系がおかしくても、上皮にバリアを作ってやればいいので、この上皮細胞のバリア機能を強化するような方法が開発されれば病気は治せるんじゃないかと思うんです。
――そのあたりのメカニズムが、いまわかってきた状況?
竹田 そうですね。消化管の上皮細胞というのは粘液層で覆われているんですが、特に大腸の粘液層はきわめて分厚いのです。
――粘液層というとつまり粘膜の……?
竹田 いえ、粘液です。上皮細胞が作り出すネバネバの液体。成分としてはムチンなどですね。粘液層ができた結果、腸内細菌が上皮に入って来られなくなっているんですよ。
――なるほど。
竹田 健康な状態では宿主と腸内細菌が出会ってないんです。
――「腸の粘膜」という言葉はよく使われていますが、粘膜はその粘液の下の……。
竹田 粘膜というのは上皮とその下の粘膜固有層を含めた組織すべてのことをいいます。実際は大腸の腸管の中です。粘液については、上皮細胞がどんどん分泌してネバネバした層ができているということです。
――その粘液が一種の保護膜みたいになっているということですか?
竹田 そうですね。粘液があるとここは無菌で、先ほども言ったように出会うことがなければ絶対に炎症は起こらないですから。実際にマウスの実験になりますが、炎症が起きているマウスはこの無菌層がなくなっていてどんどんと腸内細菌が宿主と出会っているわけですよ。
――なるほど。
竹田 じゃあ、どうしてここが無菌になるのかと問われると、よくわかっていないのですが、最近僕たちはLypd8という分子を見つけまして、ムチンと同じように上皮細胞から分泌されていると考えられます。通常は人でも同じように発現しているのですが、潰瘍性大腸炎の患者さんでは全然発現がなくなっているのです。マウスの実験でも、この分子をなくしてしまうと無菌層が無くなってしまう。
――Lypd8が炎症のカギを握っているわけですね。
竹田 その後調べてみると、Lypd8が腸内細菌の中でも鞭毛を持っているような菌と会合して……。鞭毛を持っている腸内細菌はどんどん運動しますが、Lypd8はその運動を止めて侵入を防いでいるような分子なんだと思います。鞭毛を持っている腸内細菌は運動性が高いので、粘液層に異常があればどんどんと侵入してきて、その結果、腸管炎症を起こす。僕たちにとって、本来は必要な常在細菌なのですが……。
――バリアが取れてしまうと、それが悪い働きをしてしまう。その意味ではとても微妙な層なんですね。Lypd8がなぜ減るのかとか、あるいはどうすれば増やせるのかといった点は……。
竹田 ええ、そういったところでアプローチが可能だと思います。潰瘍性大腸炎になることで発現が減っているわけですから。たとえば、病気でどうしようもなく減ってくる場合、鞭毛の動きを止めるような薬剤を開発できれば、その菌を殺すわけではなく症状が抑えられる可能性があります。今までは抗生物質などで菌を殺すという感じでしたが、そうではなくて鞭毛の動きを止めるわけです。そうした薬剤であれば、炎症性腸疾患のコントロールは可能になってくるのではないかと思います。
■ムチン層を強化する「生体絆創膏」があれば
――Lypd8は摂取できないんでしょうか?
竹田 研究室でもそれは実験しているところです。ただ、治療薬として考えた場合、タンパク質を作るわけですから高価なものになると思うんです。生物学的製剤と一緒で……。
――あまり一般的に流通できるような薬価にならないということですか?
竹田 そうですね。
――たとえば、高額でもサプリメントとして、難病の人に限定して摂ってもらうことで、症状が変わる可能性は?
竹田 ありえると思います。
――あと、ムチンというネバネバ成分というのは海藻などに含まれていると言われますよね? メカブとかオクラとかヤマイモとか、そうしたものを食べると整腸作用にいいと言われることもありますが……。
竹田 そのあたりは難しくて。よく女性の美容のためにヒアルロン酸やコラーゲンを摂ったらいいと言うじゃないですか? ただ、食べたものがどう届くのかという疑問もあるので……。
――コラーゲンは一度分解されてアミノ酸になってしまうので、それがどうやって再合成されてそこに届くかという問題はありますよね。
竹田 そうなんです。生理的なことで言えば、上皮の上にきれいなネバネバを作るということが必要だとは思いますが……。
――ただ、食品成分のムチンが都合よく腸管の上皮だけに……。
竹田 行くのかな?とは思いますね。
――因果関係がわかりづらいですよね。たとえば、疫学的にたくさんの人にムチンを食べてもらって、腸の上皮の状態を調べるとか、そうすれば因果関係がわかる可能性はありますか?
竹田 そうですね。要は、ネバネバが上皮にちゃんとくっつけば病気は治せると思うんです。だから、上皮の機能を強化するような「生体絆創膏」を作りましょうと。ムチンの代わりになるような水分だけは通すけれど、腸内細菌は通らせない絆創膏ができれば絶対に病気は治せますよと。まあ、どうやって作ればいいんだって話ですけれど(笑)。
――食物繊維のサプリメントとかありますよね? そうした成分は大腸まで届くから、それにムチンを混ぜ込むとか……。やっぱり届く前に吸収されてしまうんでしょうか?
竹田 そのあたりはどうなっているんでしょうね?
――どちらにしても予防が大事なのかなと感じました。
竹田 そうですね。炎症性腸疾患の予備軍はかなりいると思いますのでね。
――本当にひどい炎症だと生命の危機になりますが、一般の人もちょっとした炎症は日々体のあちこちで起きているわけですよね。たとえば不規則な生活やストレスで慢性的に炎症が起きているんじゃないかと。
竹田 ええ、そうなのだと思います。
――炎症性腸疾患にならないまでも、ご研究されてきたことの延長上で、「何を食べたら良い」「どう過ごせば良いか」など、どのあたりまで還元できるのかなと? ムチンの話もそうですが……。
竹田 どうなんでしょうね。僕は基礎の研究者なのでエビデンスがないことはあまり簡単には言えないところがあって、「これなら大丈夫」というのはなかなか難しいです。
■「リーキーガット」はなぜ起こるのか?
――いま、腸の上皮が食べ物によって炎症を起こすという話は一般的にもよく知るようになってきていて、たとえば「小麦のグルテンが良くない」といった話題が増えてきました。要は小麦に含まれるグルテンが炎症を……。
竹田 セリアックディジーズ(セリアック病)ですね。それはサイエンス的にも証明されてきているので、ありえることだと思います。
――グルテンだけが原因かわかりませんが、食生活の乱れで上皮細胞のタイトジャンクションが何らかの不具合を起こして、大きな分子が体内に入ったりするということはありえますよね?
竹田 ありえます。僕の中では、それも潰瘍性大腸炎の原因の一つであろうと考えています。
――潰瘍性大腸炎の方がどうしてそうなるのかはわからないにせよ、現象としてはそういうことが起こっていると。だとすれば、潰瘍性大腸炎までならないにしても、何かしらタイトジャンクションが不具合を起こすことが体調不良につながっていることはあるのでしょうか?
竹田 まだわかってないですね。先ほどお話しした、上皮層のバリアをいかに強化するかってことだと思うんですね。ストレスでそこにどうリーキーガットが起こるのかということだと思うんですが……。
――リーキーガットという現象はありえるわけですよね?
竹田 ええ、ありえます。
――でも、その原因が食事内容なのかストレスなのかまではわかっていない? まだエビデンスもそんなにないということですか?
竹田 ないですね。
――特定の疾患に対してある程度言えても、一般の人の健康に対しても普遍的に言えるようなことは?
竹田 難しいと思いますね。リーキーガットという現象が病気の原因としてあるのは事実なんですが、じゃあ、どうしてそれが起こるのかはよくわかっていないんです。実験的にも「あれで起こる、これで起こる」とか「この遺伝子で起こりやすい」というのはあるので、それらが総合している可能性はあると思うんですけれどね。
――先生もある意味ではそこを研究対象にしていらっしゃる?
竹田 そうですね。炎症性腸疾患もそこにターゲットを絞れば何かできるんじゃないかと、いま思っていて……。
――それで先ほどの話のように「どうしたらバリアが強化できるか?」につながるんですね。
竹田 そういうことです。
――あと、先生ご自身はもともと審良静男先生のところにいらっしゃって、自然免疫の分野にもずっと携わってこられたわけですよね? 自然免疫と今の研究はどうリンクしているのでしょうか? 腸に研究を特化された理由というのは?
竹田 審良先生が独立し、トールライクレセプターの解析を始める前、僕は岸本忠三先生のところでサイトカインのシグナルの研究をやっていたんです。そのサイトカインシグナルの中にSTATファミリーという転写因子ファミリーがあって、岸本先生の研究室ではインターロイキン6のシグナルを伝えるSTAT3の遺伝子に着目していたんです。
僕は大学院生としてこの研究に参加して、STAT3のノックアウトマウスを作るというのが最初の研究課題だったんですね。そのノックアウトマウスを作ると胎生致死になってしまって……。
――胎生致死?
竹田 マウスがお腹の中で死んでしまって産まれてこないので、じゃあ、組織特異的にSTAT3という分子を潰そうということで、マクロファージのような自然免疫担当細胞でSTAT3を潰していくと全身で自然免疫が過剰活性化されてくるんですが、病気としては炎症性腸疾患が起きるので、「腸の病気だけがなぜ起こってくるのか?」にすごく興味を持ちました。
その一方で審良先生が独立されてトールライクレセプターの研究を始められたこともあり、将来独立したら、自然免疫と腸管炎症で研究を始めようと思って……。まあ、経緯としてはそんなところですね。
――なるほど。この腸の疾患だけが多いというのはわりと知られてはいたことだったんですか?
竹田 いえ、それまでは自然免疫担当細胞なんて何をしているものかよくわかっていませんでしたから。ただ、こうした研究と並行してトールライクレセプターの解析を行い、そこから微生物、自然免疫、獲得免疫という流れがわかってきて、もともとそれは感染病原微生物が対象なんですが、炎症性腸疾患という病気にも同じ流れができたということです。
――なるほど。それで今日お話いただいたような流れで。
竹田 そうですね。だから免疫とひとまとめで言いますが、最初は自然免疫が腸内細菌を認識することから始まって……。
――ええと、上皮細胞というイメージで?
竹田 上皮細胞じゃなくて、上皮細胞の壁を越えたその下にあるマクロファージとか樹状細胞です。
――ああ、それが自然免疫の反応ということですね? マクロファージとかのトールライクレセプターの反応という意味合いでいいでしょうか?
竹田 そうですね。
――それでパターン認識が起きてという、そのメカニズムを審良先生が解明されてきたということですね。
竹田 そうです。上皮の直下にいるマクロファージが過剰活性化されると、トールライクレセプター依存性になって、どんどんと炎症性腸疾患が起こってくるということです。そういうアイデアもあるので、僕は上皮で分け隔ててやれば病気は起こらないだろうと考えているわけです。
■腸の代謝産物に病気の原因が隠されているかもしれない
――先生のように、免疫と腸内細菌を同時に研究をされている方ってあまり知らなかったのですが、研究者としては少ないのでしょうか?
竹田 今はもう増えてきていますね。もともと畑違いだったのが合体して、一緒になってきましたから。はじめは僕も自然免疫の異常ということに着目しましたが、研究を続けていく中で腸内環境因子の重要性も意識しながらやるようになっていきました。
――教科書的な視点かもしれませんが、代謝とか消化吸収は小腸が舞台だから免疫が働くのはこっちで、大腸は排泄器官だから腸内細菌がたくさん棲んでいて、宿主の健康に影響を与えているというふうに、大腸と小腸を無意識で分けているところがありまして……。
竹田 基本的には、やはり小腸と大腸は違うんですけども、大腸も排泄だけでなくて、腸内細菌の代謝産物、たとえばビタミンとか短鎖脂肪酸などは大腸でできてきますし、食物繊維の分解なども大腸の腸内細菌が嫌気性発酵することで行っているので……。
――結局、栄養吸収もしているわけですよね?
竹田 しています。働きが違うというのはもう絶対ですけれども。
――ですから、免疫も代謝も、小腸・大腸を含めてもっとダイナミックに捉えたほうがいいんだと改めて感じました。免疫と腸内細菌もつながりあっているからこそ、先生のご研究もあるのかなと。
竹田 そうだと思いますね。
――メタボリックシンドロームというのは代謝症候群と訳されるように、ざっくり言うと「代謝の異常で起こる」、つまり代謝は免疫とも表裏一体であるわけですよね? だとすれば、いま言われているメタボや生活習慣病も免疫に関わる部分で何か問題が起きて……。
竹田 そうですね。メタボリックシンドロームも、脂肪組織が沈着している部分では免疫細胞が侵入して炎症が起こっています。それがメタボリックシンドロームを引き起こしているのだろうということはわかってきています。
――メタボも広い意味では炎症性疾患?
竹田 そうです。
――ということは、生理的に言うと炎症が起こらないような食事なり生活をしていると(病気に)なりにくいということでしょうか?
竹田 そうだと思いますね。欧米の研究ですが、肥満の人の腸内細菌叢は全然変わってしまっているので……。腸内細菌叢は調べれば調べるほど個人差が大きくて、「結局、何なんだ?!」となってきていますけれど、先ほど言ったように、全然違う地域に住んでいて腸内細菌叢が根本的に違う人でも、基本的に健康な人は健康なんですね。それは、吸収する代謝産物は基本的にはほぼ同じであるわけがですから、代謝産物をきっちりと見ればそこにクリティカルな要因が出てくるかもしれません。
――病気になる人の原因がそこからわかる?
竹田 ええ。10〜20年後になれば病気に関わる代謝産物がわかってくるのかなと思います。炎症性腸疾患はその場で起こっているのであまりないと思うんですが、多発性硬化症のように全身で起こる病気には、何かそういった要素がキーワードとして出てくると思いますね。
――なるほど。そのあたりも病気を解明するカギの一つになってくるかもしれないと。免疫のとらえ方も、もはや感染症にとどまらず、病気全体を視野に入れたより包括的なものになっていきそうですね。
竹田 ええ。そうなっていくと思います。
――今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。
↓インタビュー第1回(前編)はこちらをご覧ください。
★「「腸内細菌はお互いがコミュニケーションしあい、生体に影響を及ぼしているのだと思います」(竹田潔インタビュー①)
◎竹田潔 Kiyoshi Takeda
1966年、大阪生まれ。大阪大学大学院医学系研究科教授。専門は、免疫制御学、粘膜免疫学。1998年、大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了。兵庫医科大学医学部助手、大阪大学微生物病研究所助手、九州大学生体防御医学研究所教授を経て、2007年より現職。大学時代より岸本忠三、審良静男氏のもとで学ぶ過程で免疫と腸の炎症性疾患の関わりに興味を抱き、サイトカインシグナル伝達の分子機構の解明、消化管粘膜免疫機構の解析、自然免疫機構の解析などに従事。独立後、潰瘍性大腸炎やクローン病などの解明に取り組んでいる。http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/ongene/
投稿者プロフィール
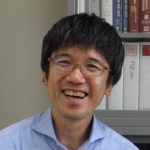
最新の投稿
 長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない
長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?
長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?
長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?
長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?