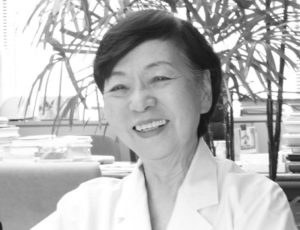共生が基本ですから、「無益な戦い」はやってはいけないということでしょう(上野川修一インタビュー②)
近年、腸にまつわる研究が世界的に注目を集めるなか、その重要なキーとして腸内細菌の生態、ヒトの健康との関わりなどが徐々に解明されてきている。ヒトは食べることでエネルギーを得て、生命活動を営んでいるが、それは単独で成り立っているわけではなく、その背後には腸内細菌をはじめとする目に見えない微生物との協力関係、すなわち「共生」がある。食品免疫学の第一人者として、食べ物とアレルギー、免疫などの関係について研究をしてきた上野川修一氏(東京大学名誉教授)に、腸内細菌研究のいまについて伺った。今回はその第2回。

腸内細菌と免疫のつながり
――初期の段階では消化と免疫が混然一体となったような形だったのが、だんだんと明確になってきた感じでしょうか? ただ、大腸の機能が確立したのはもう少し後であるということですね。
上野川 ひとつのイメージになりますが、嫌気性の大腸に外部の菌が棲みついたとしましょう。たとえば、赤ちゃんが生まれた時の腸は無菌状態で、そこに腸内細菌が入ってくるわけですね。
――光岡知足先生の研究だと、最初に侵入した好気性の大腸菌が酸素を消費することで腸内が嫌気性になり、そのあとに乳酸菌の仲間であるビフィズス菌の繁殖が始まると伺っています。
上野川 そうだと思います。
――ビフィズス菌が繁殖して、乳酸や酢酸を分泌することで腸内が酸性の環境下になり、有害な菌が排除される。それが宿主の健康につながるため、光岡先生はビフィズス菌など乳酸菌の仲間を善玉菌と呼んでいます。
上野川 そうやって菌たちは自ら生き残っている。具体的には、食べ物を分解してエネルギーに変えていくわけですが、その中には人間にとってあまり消化できないものも含まれているわけです。
――食物繊維も分解してしまうんですよね? 昔はオリゴ糖だけが注目されていましたが、難消化の食物繊維も大腸では腸内細菌が分解して、酪酸などの短鎖脂肪酸に変わると言われています。
上野川 そうですね。最近の研究で、宿主側にこうした短鎖脂肪酸を受け取るレセプターがあることが知られるようになりました。さらに菌体成分も宿主側のレセプターに反応すると言われています。
――短鎖脂肪酸が、宿主側の細胞にあるレセプターと反応する?
上野川 ええ。菌体成分については、審良静男先生(大阪大学免疫学フロンティア研究センター拠点長)がその働きを明らかにされた自然免疫のトル様受容体(TLR)と相互作用すると言われています。そうした情報によって、宿主はその細胞の性質を知るとされています。
――腸に運ばれてくる異物の種類によって、TLRがパターン認識していたということですよね。
上野川 そういうことです。いろいろなレセプターが発見されたことによって、腸と腸内細菌の相互作用、つまり、共生の仕組みがより詳細なレベルでわかってきました。要するに、腸内細菌と生体側が歩み寄って、それぞれの生存を支えているわけでしょう?
――それが共生ということですよね。
上野川 最近でも、クロストリジウムのような菌が制御性T細胞を誘導して炎症を抑えることがわかってきました。(研究が進むことで)こうした両者の関係の仕組みが徐々に明らかになっていくでしょうね。
――小腸の自然免疫が細胞レベルでの選り分けをして、そこで許容されたものが大腸に運ばれていく感じ?
上野川 そのあたりは十分に明らかとは言えないと思いますが、免疫系は排除するだけじゃなく受け入れる仕組みもあるということでしょう。
――そもそも腸内細菌は外部にいた生き物だったわけですから。
上野川 そうです。免疫系にとっては、最初はすべての物質が異物です。オーストラリアのF・M・バーネットの唱えた学説があるのですが、それは生まれてきた時に、すべての異物に反応する抗体をつくる細胞が揃っていると。
ただ、自分の体をつくっている成分は、最初に自分の体の中でつくられるため、自分の体と反応する細胞はアポトーシスを起こして死んでしまう。だから、我々の体の中では自己に反応するものがなくなってしまうというんです。
――なるほど。だから、自分以外の異物に反応するものだけが残って、増えていくわけですね。
上野川 バーネットは、それを証明してノーベル賞をもらっています。ですから、食べ物でもなんでも基本的にはすべてのものに免疫が反応するんですが、実際は反応する場合もあるし、しない場合もある。「なぜそんなことが起きるか?」というところで、ポーリー・マッチンジャーという研究者が唱えた「デンジャーセオリー」と呼ばれる説があります。
――はい、聞いたことがあります。
上野川 デンジャーセオリーというのは、免疫系には単純に自己と非自己を見分ける以外にも、自分とってデンジャラスなものとセーフティーなものを見分ける仕組みがあると。
――それは免疫寛容の仕組みを含んでいますよね?
上野川 まあ、「悪い」というのをどこで見分けているのかまだ十分にわからないですが(笑)、病原細菌は反応するけれども腸内細菌はやっつけない、それはデンジャラス(危険)ではないからという意味で考えればいいと思います。
食物アレルギーから腸内細菌研究へ
――危険ではないという判断で寛容性が生じると。
上野川 ええ。これに関連して、僕はオーラルトレランスの研究をずっとしていたんですが……。たとえば、体に抗原を入るとこれに対する抗体ができます。ところが、初めにこれを経口的に食べさせておくと抗体産生が起こらないんですね。経口免疫寛容とも呼ばれています。
――ああ、経口免疫寛容の話ですね。
上野川 そうです。30年くらい前からその仕組みを研究していました。
――アレルギーの治療として、いまではずいぶんと広がっていますよね?
上野川 広がりましたね。特に臨床的研究が行われるようになりました。
――先生の場合、免疫学であってもまず食ありき、なんですね。オーラルトレランスもその一環であると。
上野川 ええ。ですから、アレルギーでも食物アレルギーに興味を持ってその研究をずっとやっていました。
――ご研究のそもそものきっかけは?
上野川 大学でミルクタンパク質の構造について研究を始め、大学院の時にミルク・アレルギーの研究を始めました。研究対象になったのは、ミルク・アレルギーの原因タンパク質の構造です。
これは、アレルギーを起こす特定の構造があるか、という研究です。ミルクはタンパク源としては良質ですが、それがなぜアレルゲンになってしまうのかということがテーマでしたね。
通常はタンパク質を含んだ食物を摂取してもアレルギーを起こすわけではなく、逆に抑える機構があり、これがオーラルトレランス(経口免疫寛容)と呼ばれているわけです。
――研究が食品とアレルギー抑制の関係に移っていったわけですね。
上野川 たとえば、ある食べ物をとるとそのなかのタンパク質に対してだけ免疫応答がなくなる、それがオーラルトレランスなのですが、こんなことがなぜ起こるのか? 研究を始め、検証していきました。
その過程で、オーラルトレランスとは食品中のタンパク質に対するアレルギーを防ぐ仕組みと考えました。簡単に言えば、このトレランスが破られるとアレルギーになるわけですね。
――腸内細菌についての研究を始めたのは、その後ですか?
上野川 ええ。特に免疫と腸内細菌の関係に興味を持ちました。また、有益な菌(プロバイオティクス)と免疫の関係に興味を持ち、食物アレルギーをプロバイオティクスで抑えられるかについても研究してきました。
――栄養との関連もあり、腸内環境に関心が向かった?
上野川 そうですね。光岡先生とは、機能性食品について取り組んでおられた時からのご縁です。当時、私は機能性食品のワーキンググループの若いメンバーでしたが、当時は腸内細菌やプロバイオティクスについて未知のことが多い時代でした。それが、光岡先生は新しい仮説を立てて、それを次々と実証していったわけです。
――すごいですね。どうしてわかったんでしょうか?
上野川 いやあ、それは光岡先生にお聞きしたいところです。僕の場合、腸内細菌の研究はプロバイオティクスから始まり、それと同時に腸内細菌自体の研究も始まって、のちに腸管の細胞との相互作用の研究につながっていきました。
僕はそれまでタンパク質のアレルゲンの研究をしていましたが、それが生体側のアレルゲンと反応する細胞の研究へ移っていったんです。タンパクのアレルゲン、オーラルトレランス、腸内細菌と、いずれも細胞を使った研究です。
これらはすべて多くの若い研究者との共同で行われたもので、どれも彼らの協力があって進められ、様々な事実が明らかになりました。
大事なのは「共生者への心遣い」
――ところで、母乳というのは腸内細菌にとっても必要な栄養なんですよね。私たちは生まれた頃から菌と栄養を分け合ってきた、まさに共生ということが生きる土台だったという……。
上野川 腸内細菌と食べ物の関係について調べていくと、炭水化物やタンパク質、脂肪の種類や量によって、ヒトの腸内細菌叢が変わってくるわけです。それが健康状態に関わってくるわけですから、病気になる前に腸内細菌との共生をしっかりしなさいということだと思うんです。
――そこは本当に光岡先生のおっしゃっている点からベースは変わっていないんですね? 緻密になってきているだけで。
上野川 変わってないですね。光岡先生の洞察力は、本当に素晴らしいものです。
光岡先生は日本ビフィズス菌センターの理事長をされていたのですが、その後任を10年間つとめさせていただきました。その最後の5年間だったと思います、腸内細菌の研究が世界的なブームのようになったのは。
――その意味でも、やっぱり「共生」が生命科学、生物学分野のキーワードになってきそうですね。
上野川 個人的にはそう思っています。生命は共生していないと単独では生きられませんからね。だって、我々は何を食べているんですか? 我々と植物は共生しているわけでしょう? 人間どうしも共生です。そういう意味ではこの世界のほとんどが共生、ネットワークですよ。
――肉眼では見えない世界も含めてのネットワークの調和のような……。
上野川 その中のすべてを研究するのは大変だから、腸内での宿主と腸内細菌の共生は、食も絡んでくるからやはり根本的なものだろうと、そういうことで研究が進んでいるわけですね。
――自分のためだけで成り立っていない生き物どうしの関係性の中で、他者とどう調和すればいいか……。
上野川 そうです。それが共生ですから、無益な戦いなんてやっちゃいけないという話になってくるんですけどね。
――お腹の中でも戦いはないほうがいいってことですよね。
上野川 そうですね。仲のいい腸内細菌を我々の中に生かしておくことが、やはり重要だろうと思います。
――先生は「ヒトは何を食べたらいいか」という指標のようなものをイメージされているのでしょうか?
上野川 いまの食についての研究を基盤にして、「我々にとっての理想的な食のメニュができたらいいなと思いますが、非常に複雑で難しい問題ですね。
一つ言えるのは、これまで述べてきたように、腸内細菌にとって良いかどうかも考えなければならないということです。
自分だけでなく、腸内細菌の面倒も十分に見てあげなければいけないわけで、それが共生者への心遣いというものでしょう。食と生命というのは、人類に残された最大の解明されるべき課題のひとつですから。
――最近では、腸とメンタルの関わりもよく取り上げられていますね? そこにはストレスも入ってくるように、食べ物との関係だけではなく、食べている時の状況なども影響しませんか?
上野川 そうですね。たとえば、脳がストレスを感知すると副腎皮質からホルモンが出て、それが免疫系に作用することはありますね。それが神経系に作用すると、当然、腸は影響を受けますからね。
――そのあたりが「脳腸相関」ということでしょうか?
上野川 そういうことですね。
――脳の反応は腸のぜん動運動も含めてかなり関係していると?
上野川 腸脳相関の話が出る以前は、自律神経系によって心臓も腸も自ら動いているから、脳の働きはあまり関係がないと言われていた時代がありましたが、過敏性腸症候群(IBS)のように、頭(脳)でネガティブなことを考えていると下痢なったり……それは経験的にわかりますよね?
――思っているよりもこっち(腸)が主体の場合もありえませんか?
上野川 最近では、腸から脳に影響を与えているということも考えられるようになりました。腸は必要な時は自分で24時間動かないといけない。自律神経系は全部そうなっていますから、腸も原則としては自力で動き続けます。ただ、強いストレスがあった場合にそうした働きがおかしくなってしまう……基本的にはそんな感じでしょう。
特に腸にいる腸内細菌も脳に影響を与えることが明らかになりつつあります。いま世界中でいろんな人がこのテーマで研究していますから、今後多くのことがわかってくると思います。
――話がつきませんが、今回はこんなところにしたいと思います。長時間、ありがとうございました。
上野川 ありがとうございました。
(第1回はこちら)
◎上野川修一 Shuichi Kaminogawa
1942年、東京都出身。東京大学名誉教授。農学博士。東京大学農学部農芸化学科卒業。同大助手、助教授を経て、2003年まで東京大学大学院農学生命科学研究科教授。2012年まで日本大学生物資源科学科教授。食品アレルギーや腸管免疫のしくみ、腸内細菌のからだへの影響などの研究に従事。日本農芸化学会会長、内閣府食品安全委員会専門委員会座長、日本ビフィズス菌センター(腸内細菌学会)理事長を歴任。現在、日本食品免疫学会会長。紫綬褒章、国際酪農連盟賞、日本農芸化学会賞等を受賞。著書に、『からだの中の外界 腸のふしぎ』(講談社ブルーバックス)、『免疫と腸内細菌』(平凡社)、『からだと免疫のしくみ』(日本実業出版社)など多数。食アレルギー、腸管免疫、腸内細菌などに関する研究論文多数。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない
長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?
長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?
長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?
長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?