「自分の世界観が決まっていればいいんです。数値は出さなければいけませんが、問題は自分の世界観です」(中村桂子インタビュー①)
自然を観察の対象にし、それを細部にわたるまで分析することで普遍的な真理を見出す。……この数百年、そうした科学的探求が受け継がれることで、この世界の実体が鮮明に浮かび上がってきましたが、その一方で、分析が進めば進むほど、観察者である「わたし」と観察されるものである「自然」は分離されていき、気がついたら事実だけが一人歩きする味気ない世界に変わってしまった面もあります。
「生命誌」(Bio History)を提唱される中村桂子さんは、DNAの研究者として先端科学の第一線で活動されてきた一人。科学の世界のすばらしいエッセンスを大事にしながら、このつながりを取り戻すための新しい学びの体系を伝えてきました。
私たち人間は、自分もまた自然の一部であることを忘れ、それにゆえに暴走し、自ら不安を増幅させてしまう、とてもふしぎな生き物。そのふしぎさを優しく受け容れながら、目に見えるものと目に見えないもの、科学と野性をどうつないでいくか? 大阪の「生命誌研究館」を訪ね、「生命誌」の視点から、これからの私たちの進んでいく道すじについてお話を伺いました。今回はその第1回。
「一番大事なこと」を考え続ける
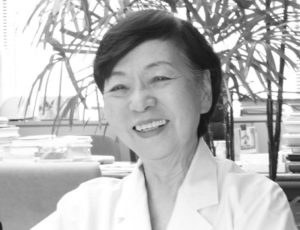
――『TISSUE』の企画を進めているなかで、たまたま先生の映画『水と風と生きものと』を拝見したんです。それがとても面白くて……。
中村 そうですか? 私自身の日常を撮影したいと言われて、「はい、どうぞ」とお任せして、それを藤原道夫監督が映画にしてくださったので、面白いと言われても(笑)。
ここ(生命誌研究館)の展示は隅から隅まで指示しますが、あの映画に口出しは一切していないんです。だから、あれは藤原作品なんです。丁寧に作ってくださいましたが。
――ここが先生の作品ということなんですね。
中村 はい。もちろんみんなで作ってはいますが、私の作品という気持ちでいます。
――映画を観ることで、そうした先生の活動がより身近に感じられるようになりました。
中村 書いたものではだめですか?
――いやいや、そんなことはないですが。ただ、先生が生命科学を通じて面白いと感じられたことを一般の人にどう伝えるかというところに、「生命誌」を提唱されたそもそもの思いがあると感じたのですが……。
中村 いえ、それは全然違います。「広める」という考え方は、私にはないのです。私はここを作る時に禁句を作ったんです。それは「啓蒙と普及」です。「啓蒙と普及」は私の辞書にはないんです。最初、私は「教育」もできないと思って「教育、啓蒙、普及は禁句」と言っていたんですが。
――そうなんですか?
中村 ただ、education(教育)はもともと「引き出す」という意味ですし、自分の年齢を考えても次世代に残すために何かやらなければいけないかなと思って、(禁句から)教育は外しました。でも、「啓蒙と普及」はいまも禁句です。偉そうに言うことでもないんですけれど(笑)、私は自分が本当に大事だと思うことをやるだけなんです。
――それが生命誌研究館であると……。
中村 はい。ここを作ったのも、私の本当にやりたいことだったからであって、誰もわかってくれなくてもやっていたと思います。生命誌研究館を構想したのは25年以上前になりますが、その時は親しい友人もわかってくれなかったですね。最近、やってきたことが目に見える形になったことで、周囲の人たちも理解してくれるようになりましたが……。
――大衆化を望んでいるわけではないんですね。
中村 正直、私はマイノリティが大好きで、何かが流行りはじめるといやになるんです。わかってもらえないのはしんどいですが、わかってもらえないことをやっている時が、一番元気がありますから。
――しんどいほうが楽しいのかもしれません。
中村 「一番大事なことは何か?」を考え続けることは大好きですが、みんなに無理にわかってもらおうとは思わないんです。理解者がいるのは、もちろん嬉しいですよ。だけど、百人の来館者が来てワイワイと見学するだけならば、3人が本当にじっくり観てくれるほうが嬉しいですね。
周縁にいるのって面白いでしょ?
――伝える仕事をしているので、「伝えたい」って思いはあるんですが、マイナーだったものが一般に知れ渡った瞬間につまらなくなるという思いは確かにあります(笑)。だから、なるべく極のところにいるようにしているんです。
中村 周縁にいるのって面白いでしょ? 私も周縁にいるのが大好き。
――面白いですね。でも、伝えたいという欲求からすると、「これをどうやったら人に伝えられるかな?」っていう思いはつねにありました。
中村 そうは言っても、私の話すのは日常のことです。私は抽象概念が全然ダメなので、「生命とは何か?」という問いに興味がないんです。同様に、「心とは何か?」、「正義とは何か?」、「愛とは何か?」といった問いも自分のなかで立てられない。それに答えるのにもあまり興味がないですしね。
――先生はどんなふうに問いを立てるんですか?
中村 「この蜘蛛が生きている」という具体的な事実があって、そこから「どうやって生きているの?」という問いが生まれ、その次に、「私も生きている。それと同じね」ということを考えて……。そうやって「生きているって何だろう?」ということを探しだすのが好きなんですよ。具体的なことから「私はどう生きたらいいんだろう?」ということを考える。「生命とは何か?」なんていう抽象概念を考える頭脳を、残念なことに持ちあわせていないんです。
――具体的なものを手がかりにしないと、実感が湧かないという感じでしょうか?
中村 体にストンと落ちるものでないと、ダメなんです。頭で理解している状況はいやなんです。哲学者たちは難しい抽象概念もストンと腑に落としているのかもしれませんが、私の能力では落ちないんです。だから、私は「生きているってどういうことだろう?」と考えた時に、蜘蛛や蝶がやっていることをまず観ます。「蝶のお母さんはスゴイことをやっているな」と思うことで、「人間のお母さんもスゴイことをやっているな……」と考えていくことができ、「生きるってこういうことじゃない?」とだんだん思えるようにもなる。私の場合、どうもそういう考え方しかできないみたいですね(笑)。
研究者は自分の論文を演奏すればいい
――ただ、先生もお書きになっていますが、科学自体に抽象概念になりかねない部分がありますよね? 研究するほどに、日常とか自分の生活といった具体的な世界から離れていくという……。
中村 (一般的な科学では)専門化するということは、より抽象化することとされていますけれど、私の場合、それが日常とつながった時に初めて自分にとっての学問になるんです。
――もしかして、そこが伝えづらかったんですか?
中村 ええ、全然わかってもらえませんでしたね。私はここを作った時、「生命誌研究館」という6文字の言葉をセットで思いつきました。生命誌をやりたくて、普及するために研究館を作ったのではなくて、生命誌は研究館でしかできないと思ったんです。
――なるほど。
中村 ではなぜ研究館かというと、いまの世の中のお約束事としては「研究したら論文を出す」ということになっています。それをやらなければ専門家としてのレーゾンデートル(存在理由)がないので、やらなくてはなりませんが、一般の人にとってそれは楽譜でしかないだろうと。
―― 一般人は楽譜は読めませんね。
中村 ベートーヴェンの「運命」という交響曲は誰でも知っている名曲で、みんなが愛しているけれど、ベートーヴェンの楽譜が置いてあっても「運命」だとわかる人がどれだけいますか? もちろん、作曲家や指揮者はわかるでしょう。でも、ほんの一握りの人たちですよね?
――そうですね。演奏を聴いて初めて素晴らしいとわかるのが、一般の人です。
中村 その時、ベートーヴェンが生きていて、演奏してくれたら最高ですよ。それが本当の「運命」でしょう? だとすると、研究者は自分の論文を演奏すればいいんじゃないかって思ったんです。「音楽は必ず演奏するのに、なぜ科学は演奏しないんだ?」って思ったんです。だから、ここをコンサートホールにして、演奏しようと考えたんです。たとえば、N響が「運命」を演奏するとします。その時に演奏を「啓蒙普及」と言いますか?
――ああ、言いません。
中村 彼らは自分の最高の演奏をします。だけど、「音楽を啓蒙普及しています」とは言いませんよね? どうして科学だけは「啓蒙普及」って言わなきゃならないの、と思ったんですよ。「私は最高の演奏をします。だからお聴きになりたい方はぜひいらしてください」というのが、科学においても本来の姿なんじゃないかと私は思うんです。
――啓蒙と普及は、確かにおかしいですね。
中村 そもそも、「私たちが最高の演奏をするから聴きに来なさい」って強制したりしないでしょ? 聴きたい方が行くわけですよね? ところが科学だと、「啓蒙普及」と称して嫌がる人を連れてこようとするんです。そんな馬鹿なという気持ちです(笑)。
――近代化の流れのなかで、そういうものがすべてセットで動いてきている部分があって、そこに胡散臭さや違和感があるのかと。
中村 私は、科学も音楽や美術と同じだと思っているので、やるべきことは、自分たちが携わっているものを最高に表現しましょうということなんです。だから、ここで何かをやる時は美しくなければいけないし、思いがこもっていなければいけない。ただ普及のために「私たちはこんなことやりました」というだけのものは決して置いてはいけないんです。自分の気持ちを込めたものを美しく表現し、それを見ていただくことが大事だと思うのです。
世界観が決まっていればいい
――先生は、「人間は生き物であり、自然のなかにいる」ということを話されていますよね?
中村 そうです。私が思っているのはそれだけです。だけど、先ほども話したように、抽象的に「生命を尊重しよう」と言っても私にはピンと来ない。「生命尊重って何?」って考えた時に、たとえば、ここに蟻が這っているとするでしょう。この蟻も親がいないと存在しませんが、その親の親のことを考えていくと38億年もさかのぼれるんですよ。つまり、目の前の小さな蟻も38億年かからないとここにはいない。それってすごいことですよね?
――生命尊重が実感につながっていきますね。
中村 どんなに立派なロボットも、パーツをひとつずつ組み立てればできてしまうけれど、38億年はかからないですよね? でも、蟻は38億年がないとここにいない。すごいことだけれども、同時にそれは当たり前のことでしょう? もちろん、人間もそのひとつであって、生き物であり、自然の一部なんです。そういうことをベースに生きていくということは、当たり前なんだということです。
――科学では、論文を書くにしても数量化って絶対に必要じゃないですか? ただ、それだけでいいのかという話につながりますよね?
中村 そうです。
――その部分が伝わりそうで伝わっていないような気がするんですが?
中村 自分の持っている世界観が決まっていればいいだろうと思うのです。数値は出さなければいけませんが、問題は自分の持っている世界観です。世界観が生き物の世界観であれば、数値はそこに吸収できます。でも、それが機械のような世界観で、こんなに格差があっても平気な世界観を持っていたら、同じ数値が違う意味を持ってしまうでしょう? ここでも毎日DNAを分析しているわけで、やることの問題ではないんです。問題は自分の持っている世界観です。それが生きるということをベースにした世界観になっていない、そこが問題なんです。
◼︎「38億年だけどごめんなさい」
――世界観ですから、当然、数字やデータには表しきれないものですよね。
中村 大事なのは、私はどう生きるか、私はどう暮らすかということだけです。大森先生が見事に書いてくださっているでしょう?
――哲学者の大森荘蔵先生ですね。
中村 『科学者が人間であること』(岩波新書)で紹介しましたが、あれが私も共有する世界観です。毎日暮らしていくなかで、ふとアフリカの人のことも考えたりするという世界観ですよ。
――大森先生は、「人間とは機械ではない何かである」「当然、命ですから機械的なものではありません」といったことを書かれています。「生きた自然との一体感」という言葉も使われていますが、一見すると、かなり抽象的ですよね。
中村 いえいえ、蟻の話と同じですよ。
――同じですか。
中村 家にいると蟻が入ってくることがよくあるので、私は蟻さんとお話するんです。ところがそんな話をすると、「私ならすぐに潰すわ」って言う人がいる。私は「潰さないでよく眺めてお話すると面白いわよ。邪魔になるなら庭に追い出してあげてよ」と言うんですが、そうすると「ゴキブリはどうするの?」って。私もゴキブリは殺虫剤をかけます(笑)。
――その違いはどこにあるんですか?
中村 台所には食べ物もあり、衛生的にも問題がありますからね。それは私の勝手なんですけれど、でも、そこが「生きる」ということの面白さなんですよ。生きることが大事だと言っても、「じゃあ、あなたは何も食べないのですか?」と問われたら、毎日食べますよね? それらもすべて生き物ですから、何も殺しませんとは言えないわけです。ただ、自分が生きていくなかで「これは」って考えながらやっていくと、「蟻まで潰さなくていいでしょ?」と……。
――なんだかわかる気がします。
中村 まあ、冗談ではあるんですが、ゴキブリを殺す時は「あなたも38億年だけど、ゴメンね」って言ってから潰すんです。だって、お米だってお肉だって、何だってそうでしょう? 38億年かかっている点は同じです。あなたも「38億年だけどごめんなさい」と思って食べているわけでしょ?
――はい(笑)。
中村 だから、私の辞書には「正義」とか「絶対」って言葉はないんです。私のやっていることは正しいから従いなさいなんて言わないけれど、でも蟻くらいは気にしてもいいじゃないって感じですね(笑)。
――それは理論というより、感覚ですよね?
中村 それを「世界観」と言っているんです。大事なのは、その世界観をどうすればいいのっていうことなんですが、その答えはひとつです。自然と接していなければ絶対にいけません。先ほど「絶対はない」と言ったのには矛盾するけれど(笑)、これは決して否定できない真実です。
――自然と接するからこそ、自然に寄り添った世界観が生まれるということですね。
◼︎自然のなかでみんなが暮らせる社会
中村 ですから、東京の高層マンションには本当に疑問を感じています。そんなところで子どもを育てるのは、本当に恐ろしいことです。
――じつは、僕たち夫婦も高層マンションに住んでいた時代があって、いろいろ経験していまは田舎のほうに移ったんです。
中村 そうなんですか?
――37階に2年間住んでいました(笑)。なかなか科学的にどうとは言えませんが、生物としては非常に不自然なことだと感じました。
中村 そう感じられたんですね。
――めったにない経験でしたし、楽しいこともたくさんありましたが、やはり鳥でもないのに常時、体が浮いているわけですから、自然とは言えません。床はありますが、大地の上にいるのとは感覚がまったく違う。そうした体験もあって、自然のなかで過ごすことの大切さはより感じています。
中村 高層階だと窓も閉じたままでしょ? そうすると「いま、風が吹いているね」とかなかなか感じられないのではないですか?
――はい。天気も気温も、下界まで降りないとよくわからないところがありました。それが普通というのは、やっぱり変ですよね。
中村 私の家は東京の世田谷にあるんですが、幸いなことに緑がとても多い場所で、エアコンを使うことはほとんどないんです。
――夏の暑い時にもですか?
中村 はい。そういう時は、必ず天窓を開けて風を通すようにしています。そうすると、暑い日にお客様が来られても、「ここは涼しいですね」って言われます。都会の家でも、うまく風を通せれば本当はエアコンなんて必要ないんですよ。
――昔の日本家屋もそういう構造でしたからね。
中村 そう。必要なら風が通るところに座ればいいわけ。そうすると我慢してじゃなく、好みでエアコンを使わないことが選べます。汗をかいてお客様が来られたら、もちろんエアコンをつけてさしあげますが、それ以外は使いません。省エネとかエコとか自然環境のためとかじゃなくて、自分が好んでやっていることなんですけれども。
――そうした感覚が最初にありきというか、それが世界観なんだと思うんですが。
中村 そうですね。私は東京の生まれですが、幸いにも原っぱのあるような場所で育ち、そうした感覚が体に染みついていますから、そこから世界観がつくられたのでしょう。ですから、子どもの教育だとかエコだとかいちいち言わないで、普通に自然のなかでみんなが暮らせるような社会にしていけたら、日本は素晴らしい国になると思います。日本人はもともとそういうことが得意で、とっても素晴らしい能力を持っている民族ですから、本当はその力を使ってただ普通にやればいいだけなんです。
↓続きはこちらをご覧ください。
★「これからは『普通に生きる』ための決心が必要かもしれません」(中村桂子インタビュー②)
◎中村桂子 Keiko Nakamura
1936年東京生まれ。59年、東京大学理学部化学科卒。理学博士。三菱化成生命科学研究所、早稲田大学人間科学部教授などを経て、93年、大阪・高槻市に「JT生命誌研究館」を設立。大腸菌の遺伝子制御などの研究を通じ、生物に受け継がれている生命の歴史に着目、「生命誌」を提唱する。2002年、同館の館長に就任、現在に至る。著書は『生命科学から生命誌へ』『自己創出する生命』『科学者が人間であること』『小さき生き物たちの 国で』など多数。2015年、ドキュメンタリー映画『水と風と生きものと〜中村桂子・生命誌を紡ぐ』(藤原道夫監督)が公開された。http://www.brh.co.jp
投稿者プロフィール
最新の投稿
 長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない
長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?
長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?
長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?
長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?



