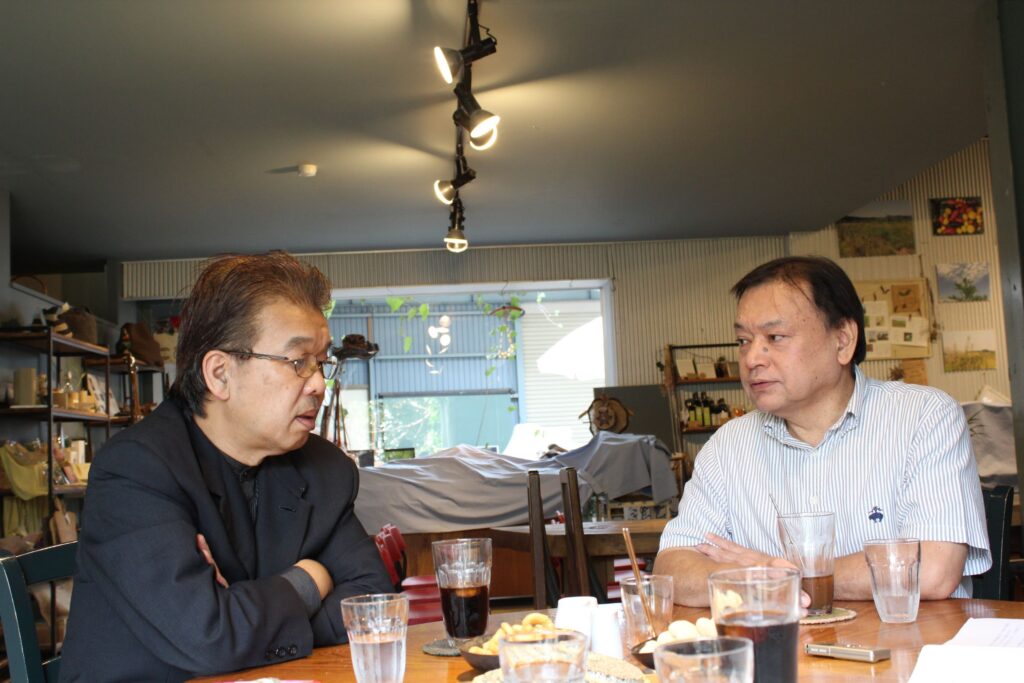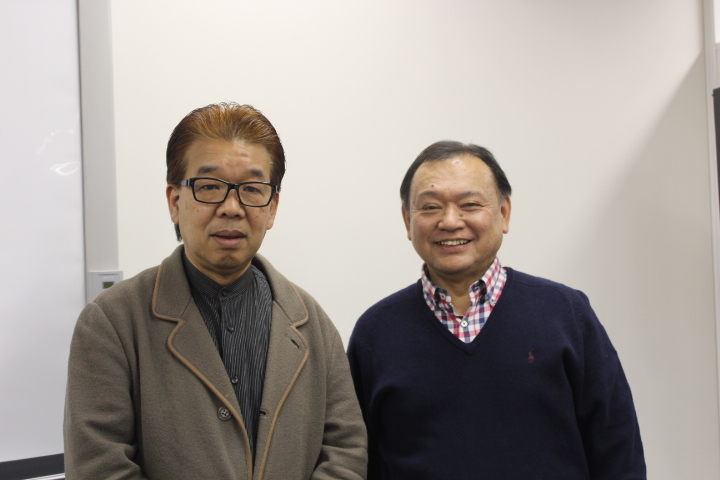「日本人は“癒しの手段”が食事に偏りすぎていると思うんです」(土橋重隆×幕内秀夫スペシャルトーク②)
2016年2月に刊行されたハンカチーフ・ブックスの『じぶん哲学〜シルクハットから鳩が出てくるのはマジックでしょうか?』。このちょっと変わったタイトルの一冊は、医師と栄養士による対談書。人はなぜ病気になるのか? 何をどう食べれば健康でいられるのか? 通常語られるのは、こんな話。でも、お二人の話はそのバックグラウンドへと私たちを誘う。
たとえば、食べるということは生活の一部、人生の一部でありながら、食べ物の栄養素だけ、成分だけが切り取られ、身体への影響が取りざたされる。医療に関しても、症状だけを見て診断がなされ、治療が行われ、その人が生きてきた過去の時間が置き去りにされる。もっと広い場所へ、歴史や文化をも包み込んだ「日常」という大きなスケールで、「生きる」ということを感じてみたくはないだろうか?
それが「じぶん哲学」。あなたにとっての、わたしにとっての、生きる哲学。その人が元気になる、じぶんらしく生きるカギ、病気になった時、治癒へと向かう底力は、数字やデータには表せない。それをどう引き出し、生きる力へとつなげていくのか? 著者のお二人に対談を振り返っていただきながら、自由に発想し、この世界で自在に生きていくためのヒントを浮かび上がらせたい。今回は後編(前編はこちら)。
食事でストレス解消する日本人
――先生は、「治したいと思うのは、悪いものを排除したい。排除することで良い状態に戻りたいという意識の表れである」と話されていますね。
土橋:治したいと思っている時は、自分は被害者で「何でこんなになっちゃったんだろう」と考えているわけです。突然、エイリアンが体の中に入り込んできたような感覚ですし、そもそも西洋医学はそういう解釈なんですね。だから「取り除こう」ということになってくるのですが、それではどうにもならないガンが実際にあるわけです。
――「仕事が病気をつくる」という言い方もされていますね。
土橋:遊びでなかなか病気にはならない。だいたい仕事が引き金なんですね。でも、早く治して仕事に復帰したいと思うでしょう?
幕内:先生に何回も言われたかな、「あなたは絶対ガンにならない」というショッキングなことを。そんな自由に生きているかな(笑)。
土橋:十分生きているんじゃないですか?
――原因ということで言えば、日本人は仕事のストレスを食事で晴らそうとしているところがあるわけですよね?
幕内:そう、結果として食事に意識が向かうんです。糖尿病が増えるのもそうした背景があって、他のところに向かえばいいんだけど、なかなかそうはいかない。アメリカの大リーガーは、成功すると「牧場をやりたい」という人が多いですよね。でも、日本人だったら「フグ食べたい」とか「ステーキがいい」とか(笑)。
――なんだかスケールが小さい気が……。
幕内:三越の地下の食品売り場とか、最高ですよ。もうまんじゅうからケーキから、フグから寿司から、ステーキ、世界中の名産……こんなに集まっている国はほかにないでしょう。クレオパトラでも食べたことないものが山ほど。自分を騙すためというか、慰めるためというか、日本人は癒しの手段があまりに食事に偏りすぎている。
――遊ぶのが下手で、食事に皆、流れちゃう。
幕内:だから、いい言い方をすれば、日本人は真面目だと言えるし、食事で癒すほうが家庭平和だし、他の遊びよりお金がかからない。いくらフグが高い、伊勢海老が高いといったって、何十万もしないですしね。だからある意味、ストレスのいい処理法なのかもしれませんが、処理が行き過ぎちゃって病気が増えていると思いますね。
土橋:日頃の仕事のいろんな問題を短時間で解消するとなれば、やっぱりアルコールとか食事になりますよね。日本はいま、そういう癒しがふんだんにありますから、本当の解決をせずにその場しのぎをする。でも、原因は残ったままなんですね。
――たしかに、食だけで解消されるわけではありません。
土橋:食に原因があるというと、何が体にいい・悪いという話になり、「何でこれを食べちゃうんだろう?」という考えにはなりませんよね。要は、一時的にでも忘れたいものがあるので、つい食べてしまう。結局、その忘れたいものが問題なのに、こういうものを食べたらこうなるという解釈になってしまうわけです。
情報で頭が一杯になっている人たち
幕内:そこはまさに、佐藤初女さんの世界とつながってくると思いますね。この間、亡くなられましたが、初女さんが主宰されていた青森県の「イスキア」って、弘前からタクシーで5000円くらいかかる場所にあるんですが、いろいろな悩みを抱えた方が泊まりにいって、食事をしていくわけですね。
――それで悩みが解決したり……。
幕内:ただね、私は3〜4回行っているんですが、ご飯は白米だし、野菜は無農薬じゃないし、醤油は普通のものだし、だから不満を持ってしまう人がいる。でも、その一方で何か大事なことに気づく人がいる。その差だと思いますね。
――気づくというのは……。
幕内:そこも帯津病院と一緒で、情報で頭が一杯になってしまっている人が多いと思うんですよ。だから、摂食障害の人も多かったと思う。ガンの人も、メンタルな病気の人もいたでしょう。そのなかで変わった人というのは、おそらく考え方や生き方を見直すことのできた人なんでしょうね。
土橋 大事なのは物質ではないと気づくんですね。
――いわゆる栄養価の優れた、高品質の食材だったり、無農薬や自然栽培の食材だったり、そうしたものを用意しているわけではない。そういう部分に、逆にカルチャーショックを受けるという……。
幕内:だから、いままでいろいろなことにとらわれていた人が、「こんな簡単なことでいいんだ」と気づく。そこに、がんじがらめのまま不満だけを持って帰っていく人との差が出るんでしょう。いま振り返って、そうハッキリと思いますね。
――土橋先生も「イスキア」に行かれていますよね。
土橋:最初に行ったのは、まだ和歌山にいた頃です。ちょうど病院をやめて「次どこ行こうかな」と思っている時、たまたま初女先生が和歌山に講演に来られたんですね。その内々だけの懇親会に、知人が呼んでくれたんです。初女さんが、目の前に座られて。私の異常な状況を察知したのか……。
――先生、異常な状況だったんですか(笑)。
土橋:ええ。後でそう聞いたんですが、「何とかしないと」と思われたんじゃないですかね。それで「来年、雪が解けた頃に一度いらっしゃい」みたいな話になって、それがいちばん最初でした。それから何度か行きましたけど、とても不思議な方で。安定した状況から飛び降りた時に、初女さんに支えられたという感じがありましたね。
――飛び降りた場所にいらして。
土橋:そんな感じでしたね。食事にしても、食材が無農薬かどうかという話じゃなく、生き物として扱ってらっしゃるんです。物質的なことにもう飽き飽きしていた自分にとって、そうした世界はすごく新鮮でした。幕内先生との出会いもそうでしたが、こうした方のおかげで再スタートが切れたように思いますね。
自分を主体に置き、自分が変化することを考える
――本のなかで、土橋先生がこんな意味のことをおっしゃっています。「自分を縛っていた枠から離れることで、結果として健康が手に入る」と。
土橋:そうですね。自分が何も変化せず、ただ治療法だけで病気を治すというのは無理があるということです。逆に変化をすれば、その治療法が何であっても、さらにそれをいい方向へもっていくことができると思うんですね。普通はいい治療法を探そうとしますが、「自分は変化はせずに」というところが問題であって、そこに気づけばいいわけです。病院に行くことで、逆に気づかないようにされちゃっているわけですね。
――病院が治癒の邪魔をしているところもあると。
土橋:結果だけで病気の説明をされて、悲観的な話を聞かされて、それで医者に完全にコントロールされてしまうということです。でも、ここまでお話しした事実がわかれば、医者とのつきあい方も変わってきますね。医者は治っても治らなくても、患者さんのことはどうでもいいんです。それは何度か病院に行かれて、医者と話をしたことがある方は感じ取っていると思うんですよね。
――医者が助けてくれるわけではないと?
土橋:そのあたりは、かなり見破られているんじゃないですか? でも、医者本人はあまり気づいていないことが多いですから、喧嘩をする必要はありません。主体は自分に置いて、自分がどう変化していけばいいかだけを考える。
――医者を利用しなさいとおっしゃっていますね。そうした気づきがあるかどうかだけでも、その後の展開はかなり変わってきそうですね。
土橋:全然違いますね。気づくというのは瞬間です。時間をかけて何かに変わるというのではなく、もう一瞬にそれがわかっちゃう。だから、いまの私のテーマはそういう瞬間をどう作り出せるか、というところですね。
具体的に「変化してください」と言っても変わりませんから、会話の中でパッと、その時にハッとね。それは顔を見ていればわかります、言葉のやりとりというより、表情が変わっていきますから。要はマジックだということに気づけば、病気への対応のしかたは変わっていくわけです。
――幕内先生、そのあたりの話をどういうふうに受け止められますか。
幕内:その通りだと思うんですが、方便としていろんなことがあると。食事もその一つだし、怪しい民間療法がきっかけになるかもしれません。たとえば、いまでもいろいろな方から「尿療法はどう思うか?」と質問されるんですね。
――尿療法ですか?
幕内:弊害は特にないでしょうし、お金もかかりませんから、私は聞かれたら「やってみたらいい」と答えていますが、それで変わる場合もある。
「尿療法」でなぜ治るのか?
――先生もやられたことがあるんですか?
幕内:以前私のいた診療所で、ある時期、いろいろとやってもなかなかよくならなかったのに、尿療法を始めたら調子が良くなったという患者さんが多かったんです。それで興味を持ったんでしょうね、院長が自分だけですればいいのに「幕内君、一緒にやろう」と。私も物好きなので拒まずに半年やったんですけど、やってよかったですね。
――半年間も? 何がよかったのでしょう?
幕内:飲んだ瞬間、涙が止まらなくなりましたから。
――すごい。それはなぜ?
幕内:道徳の破壊だったんでしょうね(笑)。その後、尿療法を調べたんですよ。尿療法を山梨のほうで専門にやっている病院があって、そこの体験記を読むとまさに一緒。長い間、尿を飲んでよくなったなんていう話は聞かない。ほとんど一瞬。要するに、それをきっかけに変わった人なんですね、先生がおっしゃった通り。
――尿の成分が体に効いて、という話ではない?
幕内:私はアンドルー・ワイルの『人はなぜ治るのか』という名著と出会ったことと、尿療法を体験したことによって、いろんな民間療法がありながら、治った人と治らない人、どこに違いがあるのかということが、なんとなくわかるようになった気がします。先生が言うように、意識が変わった。それが尿で変わった。佐藤初女先生によって変わった。もちろん、抗ガン剤、手術で変わった人もいる。
――方法の善し悪しの問題ではなさそうですね。
幕内:アンドルー・ワイルの本のなかに、こういうすごい話があるんです。ある心臓外科医が手術の際、面倒くさいから傷跡だけ縫って実際は何も治さなかった。その後、その医師は警察に捕まって、カルテから患者さんの経過を調べたら、本当に手術をした人と、何もしないでただ縫っただけの人の治癒率、死亡率が全然変わらなかった。
――確かにすごい話ですね。
幕内:(嘘の手術を受けた人は)毎日風呂に入りながら傷跡を見て、「ああ、治ったんだ」と思うわけですよね。その思いがいかに強いか。
土橋:これは聞いた話なんですけど、ある女性がガンの末期になって。どのガンかわからりませんが、末期ですから多臓器転移ですよね。「もうダメだ」というようになった女性が、「どうせ死ぬなら、ずっと憧れていた二重まぶたにしてみたい」と。それで美容外科の手術を受けたら、治っちゃったというんですね、ガンが。
――ガンが美容外科で治っちゃった?
土橋:予期したものではなかったでしょうが、二重になったらもう変わっちゃうわけですね、いままでとは違う自分に。だから、意識ですよね。
幕内:その方、ずっと目のことを気にしていたんでしょうね。人にどう思われているとか。
土橋:極端なことを言うとそういうことであって、同じことは起きなくても、同じ種類のことはいろんな形で起こせると思うんです。そういう体験をした人が、不思議な経過をたどって治っていく。これまでそういう経験をした患者さんと話をしてきたわけですけど、皆、同じですね。自然に別人になっていくわけですよ。
――病気に対してアプローチを変えたほうがよさそうですね。
土橋:そう。西洋医学であっても、代替療法であっても、その基本さえしっかりしておけば、その人の好みで西洋医学でも、代替療法でもいいと思います。こうしたことは、エビデンスなんか出せるわけがありません。しかし、そういう現実、現象をずっと見ていくと、治る人の共通点はそのあたりにあるんじゃないかなと感じますね。
――それを一人一人がただ認識するだけでも……。
土橋:なるほど、そういうことかと。今日の話でも、まず「あっ、そうか」という感じでいいと思います。「あっ、そうか」、これ大事だと思いますね。そこから始まるわけで。
民俗学者・宮本常一との出会い
――話は変わりますが、幕内先生がいちばん関心を持たれ、大事にされていることのバックボーンは、じつは栄養学ではなかったわけですよね?
幕内:私は大学を出てから専門学校に行って栄養学を教えていていたんですが、まるで算数を教えているような感じでね。要するにカロリー計算とか、栄養成分とか、私が大学で勉強したのは算数だったんです。だから、もう理屈抜きに面白くない。だって、電卓があればすむ話ですから。それで、山梨県の棡原などを訪ね、いろんな人と出会い、食べることの意味についてだんだん考えるようになったんです。
――そうやって、外の世界にドロップアウトされたわけですね。
幕内:私は、歩く旅行が好きなんですよ。だから、20代に鹿児島のいちばん南の佐多岬から北海道の宗谷岬まで3000キロ歩いたこともあります。乗り物に乗らないで、とにかく歩いた。3年前にも、東海道五十三次500キロを21日で歩いています。まあ、どれも趣味なんですが、そうやっていろんなところを歩き、その土地の食事にふれるなかで、半分冗談で「FOOD(フード)は風土」と言うようになりました。
――ベストセラー「粗食のすすめ」が生まれた、原点のようなお話しですね。
幕内:FOODは風と土が決めている。栄養士や栄養学者が決めるんじゃない。そうしたなかで出会ったのが、民俗学者の宮本常一という人なんです。
――先生のバックボーンの中心にいる人物ですね。
幕内:庶民の暮らしのなかに、その時代その時代、良かれと思って営々と築かれてきた庶民の食事というものがあるんです。それは人体実験の歴史とも言えるし、生き方の知恵とも言えるし、要はそれが大事だと思うんです。
――宮本常一は、そうした庶民の歴史を見てきたわけですね。
幕内:戦前から戦後の日本が大きく変わる時代に、民俗学者として日本じゅうをくまなく歩いたんですね。私が歩いたのはただの趣味ですが、宮本常一はそこから一つの学問を打ち立てた。こんな人がいるのかと驚いて、彼の本を読んで、なおさら歩くことの大事さを教えてもらった気がします。
土橋:私は、幕内先生に会ってから民俗学の世界を身近に感じるようになりましたが、そういう人の暮らしに注目していかないと病気を本当には理解できないし、どう治していくかということもわからないなと思うようになりましたね。
幕内:宮本常一の著作集を一言で言うと、代表作のタイトルがすべてです。『忘れられた日本人』というんですが、どこかのおじさん、おばさんがつくった食事は忘れられちゃうわけです。徳川家康が何をやったかは残ってもね、切り捨てられてしまうものがたくさんある。でも、そういう無文字の世界にこそ、生きることの本質があるんじゃないかと。私の考え方は、宮本常一と出会って大きく変わった気がしますね。
数字だらけの世界はいつから始まったのか
――ご本人とお会いしたことは?
幕内:私が気づいた時にはもう亡くなられていたので、本人と会ったことはないんですが、奥様がまだ健在だったんです。お住まいのあった山口県の周防大島まで訪ねていったことがあるんですが、とても魅力的な奥様で。どうでもいい話ですが、宮本常一自身も魅力的な人なんですよ。女性にとってもいろいろと。
――モテた人だったんですか(笑)。
幕内:それに対していろいろ言う人がいるんですが、奥様はやっぱりすごいですよ。そういう人の奥様は、「いろいろあったっていいじゃない」の一言でしたから。
――貫禄がありますね。
幕内:初めて訪ねた時に驚いたのは、まだお昼前だったのにサザエだのアワビだのエビだの焼いているんですよ。それで、いきなりビールが出てきて。奥様はその時、94歳くらいだったのかな? 「まぁ一杯いきましょう」って、そのおおらかさがね。午前中から飲むのか、いいなあと思いながら、お話しさせていただきましたが。
――宮本常一が探究した無文字の世界というのは、こうしているいまも進行していますよね。我々の日常のなかにも当然あるわけで……。
幕内:それはもう圧倒的に、無文字ですよ。(宮本常一は)それを教えてくれたんですね。
土橋:数値やデータとは違う生きることそのもの、そこから歴史が生まれるわけですね。民俗学となるとスケールが大きいですけれども、自分だけの人生だったら、自分自身の民俗学があって、病気にしてもそこに原因というものが隠れている。
幕内:「女性がダイエットを始めたのはいつからか」という話があって。西洋式の洋服を着るまで日本では着物でしたから、ウエストという発想はなかったんだといいますが、それだけじゃなく、先生が言う数量化ですね。いま考えると、宮本常一が活動していた時代には、血圧を計っている人もいなかったでしょうし、体重を計っている人もいない。もちろん、ウエストを計ってそれを気にする人もいない。数量化があまりされていなかったわけです。一方、いまの日本人は、血圧、血糖、体重、ウエスト、平均寿命。もちろん、年金、偏差値、営業成績……もう数字だらけだと思いますね。
空間を変える、空間を超える
――この数字だらけの世界から抜け出せた人がもともとの生き方というか、無文字の世界、日常の世界に気づき、場合によっては病気が治ったり……。
土橋:そうなるためには、医者がどんな存在なのかということをちゃんと知る必要があると思いますね。たいしたことないんですよ、数字の世界というのは。コンピューターでもできるような仕事をやっているわけですからね、まず数字のマジックから自分を解放されれば、いろいろなことが見えてくると思います。
幕内:医者がたいしたことがないという意味では、『ディア・ドクター』という映画を見ると面白いかもしれません。笑福亭鶴瓶が演じるニセ医者の物語なんですが、このニセ医者が無医村に行って、どんどん患者さんに慕われて。ところがある時、おばあちゃんの娘さんが都会からやって来た医者だったことで、バレちゃって。それで逃げちゃうというわけですが、バレるまではものすごい信頼を得ていたわけです。
――まさにマジックですね。
幕内:だから、いまのような医療が続くかぎり、これからニセ医者が山ほど出てくると思いますね。だってパソコン眺めて、数値から病名を診断して、この薬かと当たりをつけて、それくらいなら誰でもできますからね。
土橋:医者の評価が急激に変わっていくと思いますね。そのなかで混乱もあるでしょうが、本質がわかるいい医者が出てくる可能性もあるはずです。患者さんも変わり、医者も変わるというのが次のステージに求められることでしょうね。
幕内:中島みゆきなんかはそうなんだろうなと、対談で話しましたが。
――そういう話にいきなりなって(笑)。
幕内:中島みゆきは医者の家系で、医者の枠に収まりきらないものを歌に託して、たくさんの人を癒してきたと思うんですね。先生が言おうとしていることを、歌の世界でいち早く実現させてきたというかね。「時代」という名曲があるじゃないですか、震災の後、あの歌を聴いて涙が止まらなかったですよ。
――歌の力で、たくさんの人を治してきたのかもしれないですね。
幕内:ああいう人の歌って、百年後も確実に残るんですよ。そういう詩を書ける人の経歴を調べると、弟も医者だし、お父さんも医者だし。
――産婦人科だったんですよね。
幕内:お父さんはお父さんでもちろん立派な医者だったんでしょう。でも、それを超えている。井上陽水だって、3浪もして歯科大受からなかったんでしょう? あんな感性を持っていたら、絶対受かるわけがないですよ(笑)。
――外れたことで、もともと持っていた力が発揮できたんでしょうかね。外れたほうが枠が広がり、もともとの世界につながれるのかもしれません。
幕内:きっと親の後ろ姿を見ながらいろいろ感じていて、成人した時にはもう飽き足らなくなっていたんじゃないですか? 医者は医者で大事な仕事だけれども、無意識のうちにもっと広い世界を選んだんじゃないかと思いますね。
土橋:私は飽き足りなくなるまで20年もかかったわけですけど、空間を変える、空間を超えることで、その広い世界に飛び出した気がします。検査結果については数値化も可能ですが、元気であることは数値では測りきれません。その測りきれないものにどうつながっていくか、生命を蘇らせるか、それが一人一人のテーマになってくるはずです。
*この対談は、2016年2月27日開催の「ハンカチーフ・ブックスCafe Vol.1〜『じぶん哲学』出版記念トークショー」の内容をもとに再構成したものです。
(プロフィール)
土橋重隆 Shigetaka Tsuchihashi
外科医、医学博士。1952 年、和歌山県生まれ。78年、和歌山県立医科大学卒業。81年、西日本で最初の食道静脈瘤内視鏡的栓塞療法を手がけ、その後、2000例以上の食道静脈瘤症例に内視鏡的治療を施行。91年、和歌山県で最初の腹腔鏡下胆嚢摘出手術を施行、8年間に750例以上の腹腔鏡下手術を行う。2000年、帯津三敬病院にて終末期医療を経験、三多摩医療生協・国分寺診療所を経て、現在は埼玉県川口市に自由診療クリニックを開業。著書に『ガンをつくる心 治す心』(主婦と生活社)『50 歳を超えてガンにならない生き方』(講談社+α新書)、『死と闘わない生き方』(ディスカヴァー・トウェンティワン /玄侑宗久氏との対談)などがある。http://tuchihashi-world.jimdo.com
幕内秀夫 Hideo Makuuchi
管理栄養士。1953(昭和28)年、茨城県生れ。東京農業大学栄養学科卒。学校給食と子どもの健康を考える会代表。日本列島を歩いての縦断や横断を重ねた末に「FOODは風土」を提唱する。現在、伝統食と民間食養法の研究をする「フーズ&ヘルス研究所」代表。帯津三敬病院にて約20年にわたり食事相談を担当。ミリオンセラーになった『粗食のすすめ』『粗食のすすめ レシピ集』(ともに東洋経済新報社)をはじめ、『夜中にチョコレートを食べる女性たち』(講談社)、『変な給食』(ブックマン社)、『「健康食」のウソ』(PHP 新書)、『世にも恐ろしい「糖質制限食ダイエット」』(講談社+α新書)、『ドラッグ食(フード)』(春秋社)など著書多数。新刊に『医・食・農を支える微生物〜腸内細菌の働きと自然農業の教えから』(創森社/姫野 祐子との共著)がある。http://fandh2.wix.com/fandh
投稿者プロフィール
最新の投稿
 長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない
長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?
長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?
長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?
長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?