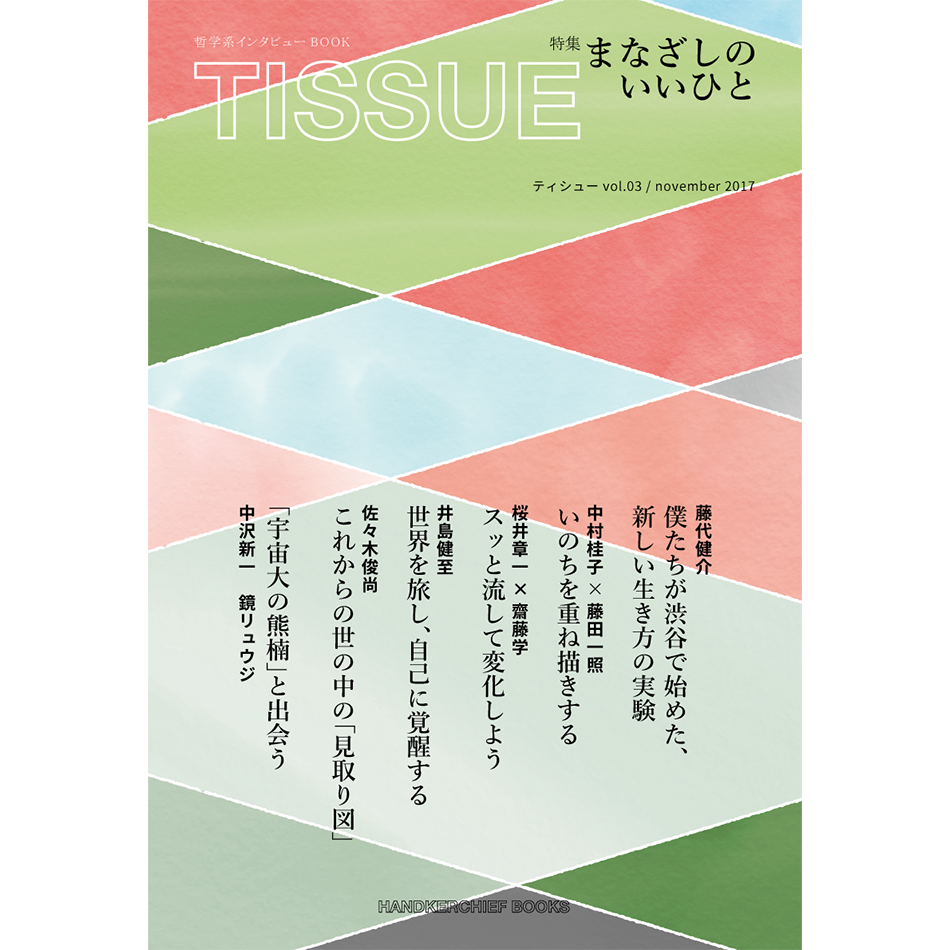「頭の中の理解だけにとどまらず、『ストンと腹に落とせる』のが日本人じゃないかと思うんです」(中村桂子×藤田一照 スペシャルトーク②)
生命科学というと、自分たちの日常とはどこか遠い、特別な世界の話のように感じられるかもしれません。
しかし、生き物の「いのち」を扱っているのが生命科学です。それが遠い場所にあるのだとしたら、どこかがおかしい。そんな思いで科学の世界のおもしろさ、生命のいとおしさを紡いできた、生命学者の中村桂子さん。
私たちが生きているバックグラウンドには、生物が歩んできた38億年の歴史(=生命誌)がある……そんなドラマの語り部である中村さんに、ぜひいちどお話ししてほしいとお願いしたのが、禅僧として多方面で活躍する藤田一照さんでした。
禅と生命科学。こちらも一見すると遠い場所にありそうですが、共通項になるのは「いのち」を見つめるまなざし。たがいの世界観が混ざり合って、この現実の中で「強く、優しく」生きていくための言葉が生まれたなら……。2017年2月、中村さんのドキュメンタリー映画『水と風と生きものと』の上映会のあと、初対面したお二人のトークが始まりました。今回はその後編(前編はこちら)。
まど・みちおの詩が語るもの
中村 そのお話と関連するかもしれませんが、まど・みちおさんが「蚊」の詩をたくさん書いていらっしゃるんです。いま、「まど・みちおの詩で生命誌をよむ」というラジオ番組をやっているんですが、その内容をまとめた本(注2)にまどさんの「蚊」の詩を全部取り上げたんです。いまおっしゃられたように、蚊が寂しそうにとまっているとかあるんですよね。
藤田 ああ、ありますね。ちょうど(持参していた本を)開いたページにありました。これもご縁ですね(笑)。
(中村さんが朗読を始める)
蚊も亦(また)さびしいのだ。
螫(さ)しもなんにもせんで、眉毛などのある面を、しずかに触りに来るのがある
中村 普通はそんなこと考えもせずに蚊が飛んできたらバン!とやっちゃいますよね? ところがまどさんは、蚊がフッととまったらこういうふうに思う。ここが私がまどさんを好きなところなんです。
藤田 (こうした日常の捉え方を)略画と呼ぶのはどうなんでしょうか? 略画というより、ものすごい密画のようでもあり、これを略画というのは申し訳ないような気がするんです。
中村 日常だから全部が略画というものではないということですね。たしかにとても細密に心の働いている略画は、密画と呼んでもよいかもしれませんね。まどさんの詩は全部そうだと思います。
藤田 僕もじつは坐禅についての本を書いたんですが(『現代坐禅講義』)、その中にまどさんの詩を引用しました。言いたいことをすごくやさしい言葉で、しかもイメージがパッと湧くようなものなのですごく助かるというか。
中村 助かりますか(笑)。
藤田 はい(笑)。だからこの『まど・みちおの詩で生命誌をよむ』というタイトルを見た時に、先ほどの岡田先生の「細胞の社会」ではないですが、すごくピタッとくるというか、ものすごくタイムリーだなと。(今回の対談が)決まってからこの本が出たので、おっしゃるように、これもまたご縁だったなと。
中村 確かにそうですね。
藤田 せっかくなのでひとつ質問させてください。僕がずっと持っている疑問なんですが、僕らは生き物であり、いわば、生きている物質ですよね? 生きている物質と死んでいる物質の決定的な違いというのは? 僧侶としては臨終の席とか、僕自身も肉親が亡くなる場面に何度か立ち会っていますが、そこで何が起きるのかというのが……。略画的に言えば「昇天した」とか「天国へいった」となるのでしょうけれど、密画でいうと生き物が死に物になる時、何が起きるといえるのでしょうか?
中村 言い逃れるわけではありませんが、じつを言うと、生物学では「生き物とは何か」という定義はまだできていないんです。もちろん科学的に、教科書的に言えば生き物というのは水のようにつながっているのではなくて、「藤田さんは藤田さん、私は私」というふうに区別されていてきちっと境界があってまとまっているものです。そして、必ず代謝をしています。
たとえば、マイクがここにありますが、それはここにあるというだけです。でも、私がここに来れば必ずここの空気を吸うわけです。吸って、出して、吸って、出してということを必ずやります。酸素は代謝と関わります。三番目が「複製をする」ということです。DNAを持っていて自分を作って子どもへとつなげていく。四番目が「進化をする」ということです。どんどんと変わっていく。だから38億年前に生き物が生まれましたが……。
藤田 それは(生き物の定義を)全部を備えたものですか?
中村 そうです。すべてを備えたものが生まれたんですが、もしも進化ということがなかったら、いまでもその当時の生き物がいるわけで、私たちなどいるはずがありません。いまいる生き物はいないはずなんです。だから、あるものからどんどんと変わって新しいものを生み出していく。それが生き物です。このマイクは進化はしませんでしょ?
藤田 人間が作っていけば違いますが、それ自身がやることはないと。
中村 そうです。生き物はそれ自身が進化をするんです。でも、これは教科書的な定義です。生き物というのはどういう性質かということはすべての教科書に書いてありますが、それがわかったからといって亡くなった方についてわかるわけではありません。
もちろん、そこで代謝が止まります。それは確かなのですが、「だから生き物って何?」と聞かれても「これぞ!」という答えはなくて、私はその時々に自分の感じていることを答えます。ある時は「時を紡ぐもの」と答えます。私たちは一瞬、一瞬どんどんと変わっていって、必ず時を紡ぎます。残念ながら最後は死というところへいくわけです。
ストンと落として何かをやる
藤田 時を紡ぐのが終わると?
中村 最後は死に行き着くわけですが、私たちが生きているとは何かと問われたらそんなふうに答えることもあります。それから、ある時は生き物とは「矛盾の塊」と答えることがあります。たとえば、無駄はないほうがいいとされますね? ですが、免疫では何億という免疫細胞を作って外敵に備えます。そして「ああ、今日は私が役割をする外敵は来なかった」となったら死んでいくんです。たいへんな無駄をしています。でも、それがないと私たちは生きていけません。「無駄だ」とか「変だ」と思われることを全部なくしていくと「死」にたどり着いてしまうんです。だから、「矛盾があるから生きている」と思わざるをえない時があるんですね。
「時を紡ぐもの」であったり、「矛盾の塊」であったり、決定的な答えはないのですが、「生き物らしさ」をひとつの言葉に限定しないで考えていくのがいいのではないかと思うんです。死についても「これが正解」というのは科学的にはありません。
藤田 科学というのはいつでも仮説で、仮説を反証するような証拠が出てきたらいつでも変えていくんですよね。頑固に変えない人もいるかもしれませんが、建前としてはオープンエンドでいつでも変わっていくもので、それこそ進化していくものであるという点が、科学の素晴らしいところだと思います。
中村 科学者に質問される方は必ず答えを求めますが、私たちが日常で一番大切にしていることは「問い」なんです。立派な功績を残した科学者は、それまで誰も考えなかったような新しい問いを立てた人なんですね。新しい問いを立てると良いお仕事ができる。だから「問いを見つけること」が科学なんです。もちろん、問いを見つけたらその答えを探し始めますが、たいていの場合は「これで終わり!」という答えは決まらないですね。たとえば、宇宙がそうですね。宇宙137億年の歴史があって、急速に解明されてきたと思ったら、またダークエネルギーなどが出てきて……。
藤田 (宇宙の)4%しかわかっていないといわれていますからね。
中村 そう。とんでもないものが出てくるわけです。進めば進むほど、わけがわからないものが出てくるのが科学とも言える。そしてそれを楽しめるのが科学者なんです。答えがないと落ち着かないというなら科学者には向きません。
藤田 もう一つ質問したいのは、「次の文明」、「次の科学」というふうに、映画の中で「次」という言葉を何回か話されていましたが……。
中村 そうですか? 私はいまの社会、特に21世紀に入ってからの社会は、「人間も生き物のひとつだ」と考えている立場からすると、とっても生きにくい社会になっているという実感があるんです。たとえば、〝HATE〟(ヘイト)という言葉はありえないですよ。人類73億人は全部同じルーツから出ているんです。だから、兄弟げんかはありますが〝HATE〟ではないでしょ? ちょっとしたいさかいが起こるのは生き物の世界の常ですが、〝HATE〟という言葉は、この中からは出てきようがありません。そんな言葉がこんなに日常の中に出てくるなんてかつてはなかったと思うのです。
藤田 仏教では、普通の人間のことを「凡夫」といいます。この凡夫の特徴は、「事実に注文をつける」、「不平不満を持ってしまう」という点なんですが、それは人間の特徴でもあると思うんです。事実に文句を言っては変えていこうとするのも人間の能力で、科学やテクノロジーを発達させた原動力ですよね。
単に知りたいだけで終わらずに、知って利用して自分の都合のいいように周囲を変えていこうとするのも人間の生き残りの戦略だったのでしょう。ただ、いかんせん歯止めがきかず、暴走してしまっている。その結果、いまの生きやすくするために作ったはずのシステムや社会が、人間にとって逆に生きにくい社会になってしまっています。
中村 生きにくくしてしまいましたね。小さな気持ちであっても、「こういうふうに考えるんですよ」ということを一人でも多くの方と共有し、何かが変わっていくといいなと思うんですが……。
藤田 こういうことは、浅い知識で終わらないで、ハートとかソウルに臍落ちすることが必要ですよね。
中村 考えをただ共有するというのとは違うんです。先ほど、科学としては世界中の仲間が生命誌絵巻を認めてくれると話しましたが、それはおそらく「頭」で認めてくれているんです。それは共有のための基盤だと思いますが、そこから体にストンと落とす時には文化によって違う。お釈迦様から始まった仏教も含めて、日本人が取り入れた文化はその「ストン」ができると思うんですが、違いますでしょうか?
藤田 そうだと思います。でも、自動的にはそうならない気がしていて……。
中村 ストンと落ちたからといって、その人が何かがすぐにできるとか、力を持って何かを成せるということには必ずしもつながりません。ただ、私はストンと腹に落ちる人が多いのが日本人じゃないかなと思っているんです。
オーガニック・ラーニングのすすめ
――禅でも「ストンと腹に落ちる」ということがテーマだと思うんですが?
藤田 落ちていなかったら出直して来いと言われる感じがありますよね(笑)。こうしたことは、口頭で教えることも必要ですが、一緒に暮らしていく中で「こんな時はこういう眼差しで見るんだとか、こういうふうに触れるんだ」とか、実際に経験して、からだで学ぶのがいいと思うんです。
僕はこれを「オーガニック・ラーニング」と呼んでいるのですが、子どもって、母国語を覚えたり、歩き始めたりするのに別にテキストや授業があるわけでもコーチがいるわけでもないのに、あらゆることを吸収して知らぬ間にできるようになりますよね? ボキャブラリーを文法に従って組み立てることで無限に文章を作り出したり、日常の動作も同じく「こう動けばこうなって……」ということを無限に生み出していけます。
いまはみんな学校の授業のようにやっているでしょう? 先生がいて、テキストがあって時間割があって。それも必要かもしれませんが、こういう新しい世界観が臍落ちするようになるには、やっぱりそうではない方法が必要かもしれません。
中村 「言う」ことも大事ですが、もっと大事なのが「聞く」ことだと思うんですね。だけど、聞いてないなあと思う人がいっぱいいる(笑)。柔らかく捉えることが大事ですが、それはまず「聞く」という容れ物を持っていないとできないと思うんです。だから、私はディベートが嫌いなんです。子どもたちにディベートを教えようとか言いますが、あれは「言うだけ言って負かせばいい」感じでしょ?
そうではなくて、私たちがいま持っている「知」というのは、すべて「対話」から生まれているんですね。お釈迦様もそうだし、ソクラテスも孔子もそうです。何か素晴らしいことを生み出した方たちは、みんな対話をされたんです。子どもたちにもディベートではなくて「対話をしようね」という雰囲気にしたいなと思うんです。
藤田 対話といえば、人と人もありますが自然との対話も大事ですね。
中村 そうです。あらゆるものとの対話です。生命誌研究では対話しています。対話しないと教えてくれませんから。本当に面白いですよ。いじめて「お前なんとかしろよ」なんて言っていてもダメで、やっぱり大好きで対話していると答えを教えてくれるんです。
藤田 いまは二次的、三次的な知識ばかりで、一次的な知識が少ないですよね? 直接生き物に触れることが、汚いとか、虫自体が減っているとか、都会だからとかいろんな理由で減ってしまっていてすごく危うい感じがします。それは自然との対話がないのと同じですよね。こちらの見方次第で見えなかったものが見えてくるようになる、そう問いかけると答えてくれるものが対話でしょう?
中村 本当にそのとおりです。自然との対話は大切なんですが、それが減ってきてますね。
藤田 こうしてご本人とお会いして、中村先生がマインド(頭)ではなく、ハートやソウル(魂)のところでわくわくしながら活動されているのがとても伝わってきました。まさに生命誌的な生き方をされているのが感じられ、今日は対話できて本当によかったです。ありがとうございました。
中村 こちらこそありがとうございました。
注1 NHK教育『こころの時代~宗教・人生「心はいかにして生まれるのか―脳科学と仏教の共鳴」』2017年2月5日放送。
注2 『NHKカルチャーラジオ 科学と人間~まど・みちおの詩で生命誌をよむ』(中村桂子 NHK出版)
中村桂子 Keiko Nakamura
1936年東京生まれ。59年、東京大学理学部化学科卒。理学博士。三菱化成生命科学研究所、早稲田大学人間科学部教授などを経て、93年、大阪・高槻市に「JT生命誌研究館」を設立。大腸菌の遺伝子制御などの研究を通じ、生物に受け継がれている生命の歴史に着目、「生命誌」を提唱する。2002年、同館の館長に就任、現在に至る。著書は『生命科学から生命誌へ』『自己創出する生命』『科学者が人間であること』『小さき生き物たちの国で』など多数。2015年、ドキュメンタリー映画『水と風と生きものと〜中村桂子・生命誌を紡ぐ』(藤原道夫監督)が公開された。http://www.brh.co.jp
藤田一照 Issho Fujita
1954年、愛媛県生まれ。東京大学教育学部教育心理学科を経て、大学院で発達心理学を専攻。28歳で博士課程を中退し禅道場に入山、得度。33歳で渡米。以来17年半にわたりアメリカで坐禅を指導する。スターバックス、フェイスブックなど、アメリカの大手企業でも坐禅を指導し、曹洞宗国際センター所長を務める(2010〜18年)。著書に『現代坐禅講義』(角川ソフィア文庫)、『禅僧が教える考えすぎない生き方』(大和書房)、『僕が飼っていた牛はどこへ行った? ~「十牛図」からたどる「居心地よい生き方」をめぐるダイアローグ』(ハンカチーフ・ブックス)など。共著に『感じて、ゆるす仏教』(KADOKAWA)、『禅の教室』(中公新書)、訳書に『禅マインドビギナーズ・マインド2』(鈴木俊隆著、サンガ新書)、『禅への鍵』(ティク・ナット・ハン著、春秋社)など。http://fujitaissho.info
投稿者プロフィール
最新の投稿
 長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない
長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?
長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?
長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?
長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?